カツカツといつもより高めのヒールを鳴らして歩く。
今日のコーディネートテーマは〝バリキャリのオーラ漂うかっこいい女性〟だ。
我ながらなかなかキマっていると思う。まぁ、結構良いお値段したし。値段相応の仕上がりに口角が自然と上がる。
服装も何もかも新しく買い直した。全て自分のお金で。新居に彼の香りや思い出、それから買ってもらったものを持ち込みたくなかったからだ。彼に頼り切らず、仕事をこなし、貯金しておいて本当に良かったと思う。
ふと足を止めて、お店のショーウィンドウに映った自分の姿を眺める。口紅は、はっきりした色を選んだ。新しくおろしたバーガンディの口紅。驚くほど自身に馴染んで似合っていた。私もいよいよこんな色が似合う歳になったのだなぁ……としみじみ感じる。
住み慣れた彼との住まいを出ていくことになったが、少し寂しい気持ちはあるけれど、ただそれだけ。
未練も怒りも焦りも悲しみもない。尊敬も愛想もとうに冷めてしまった。けれどそれに対して罪悪感だとか、そういうものは一切感じない。もともと、私はこういう人間だ。
他の人よりちょっと見切りが早いというか、なんというか……
彼とはここできっぱりとお別れ。もう二度と会うこともないだろう。
足取り軽く心の底から爽快感を感じながら、私は目的地に向かう。
「さぁ、今日は飲むぞぉー!」
まぁ、それなりに好きでしたよ。
ジェイド先輩
●
────きっかけは些細なことだった。
まぁ、今となっては、どうしようもないけれど。
昨夜のニュースでは今日の天気予報は快晴で、夜まで雨などもないとの予報だった。
朝起きると予報通りよく晴れていたから、洗濯をすることに決めた。
この天気ならよく乾くだろうなぁ……と思って、ベッドのシーツやらをまとめて洗ってしまおうと意気込む。二人分のベッドシーツや枕カバーなど、洗えるものは全て剥ぎ取って洗濯機に放り込んだ。洗っているうちに替えのシーツたちをセットして綺麗に整える。なかなかの出来栄えに私は満足して少し笑った。
そうこうしているうちに、洗濯が終わったと洗濯機から合図が聞こえ、一息つく間もなく足早にそちらへ向かう。脱水まで終えたシーツたちを外の物干し竿にかけて、次は服を洗濯機に放り込む。先に乾きにくいものから乾そうと思って、服を後回しにしたからだ。
次々と洗濯機に放り込んでいると、たまたま偶然目に留まった。彼の真っ白なシャツの首筋に赤いシミが付着している。赤ワインかソースのシミかな……? とも思ったが、こんな位置に普通ソースやワインを飛ばす人はいないだろう。擦ってみると、それはジワっと滲んだ。
多分、これは口紅だ。
この世界の住人は男女関係なく化粧をするみたいだけど、彼はこんな派手な色をつけないし、他人の口紅が恐らく付着したのだろう。
なんとまぁ、こんなテンプレのような展開が私の身にも起こるなんて、ちょっとびっくりだ。浮気にしても、もっとスマートに痕跡一つ残さずにする人だと思っていたのだが、どうやら見当違いだったようだ。まだ断定できないが、一応記憶しておこうと思う。
何かあったときのために。
手にしたシャツのシミ部分を丁寧に指先でなぞる。最近お気に入りの曲で鼻歌を歌いながら、その箇所に漂白剤を浸み込ませていった。かの有名な問題児だらけのナイトレイブンカレッジに四年間在籍し、ハプニングだらけの日常だった彼女はこのくらいでへこたれ、ショックを受けるような柔な人間ではなかったし、無論タダで終わらせる気もなかった。
綺麗にシミが取れたシャツの首筋をご機嫌に眺めながら、彼女は微笑み呟いた。
「一回目」
●
ジェイド・リーチは美しく、そして恐ろしいほどに狡猾で隙のない男だった。
その端麗な容姿から学生時代から女性は選び放題、引く手数多だったろうに、彼の執着は一人の少女に注がれていた。その相手とは、お察しの通りオンボロ寮の監督生であるユウなのだが、当の本人は全く彼からの好意に気付いていなかった。我がことながら色恋には鈍かったな、と思う。
学生時代、彼との接点は然して多くはなかった。それなのになぜ今、同棲までしているのか。答えは彼からの猛烈なアプローチによるものだ。半場無理矢理と言っていいかもしれない。
四年間の学びを経て、ナイトレイブンカレッジを卒業するという時になっても、ユウだけは進路が決まっていなかった。この時ばかりは流石の私も焦燥感と言い知れぬ不安を感じて、周りの生徒が眩しくて、元の世界に帰りたいと何度切実に思ったかしれない。この頃には学園長の方も色々と調べつくしていて、元の世界についてあらかたのことはわかっていた。
─────結論から言って、私は帰れない。
正確には帰る術はある。しかし、それは叶わない。
こちらの鏡が元の世界へと繋がるのは、千年後だと伝えられた。暦や月の位置、天体や魔法的観点から判明したそうだ。
勿論、伝えられた時はショックだった。悲しかった。
帰りたいと、いつかは帰れると思っていたから。
だけど、泣きたいとは思わなかった。私はやけに冴え切った思考の片隅で、これからの段取りについて、あれやこれやと物思いに耽っていた。
帰れないなら、次の手を考えるしかないのだから。仕方なかった。今考えれば、一種の心の防衛反応だったのかもしれない。
一通り話を聞き終えて学園長室からオンボロ寮に帰る道すがら、どこかさっきまでの説明や元の世界に帰れないことが、他人ごとのように感じられた。涙の一つも零れない自分に、「薄情な奴だなぁ」と思った。泣きたいとは思わない。嘆き悲しんで、喚いて誰かに縋りたいとも思わない。けれど胸の内がじくじく痛んで痛くて、その日は早くに寝てしまった。
その特殊な境遇や環境から、ユウは進学するにも就職するにも、随分と不利だった。
まず、魔法が使えない上に、この世界の知識常識に疎い。おまけに男子校から前代未聞唯一の女子卒業生。名門校の卒業資格は与えられても、あまりに特殊な経歴から説明するのも理解してもらうのも難しい。
この癖の強い生徒の揃う学園で必死に授業に食らいついてきたが、それでも周りとの差は明らかだった。
特別秀でた所もない、異例の存在を受け入れてもらえる場所は、未だ見つからなかった。
卒業式前日まで奔走しても進路が決まらない。もうこの時はお先真っ暗すぎて、全てが悲観的に思えてしまうところまで参っていた。
卒業式を、友人たちと笑顔で晴れやかな気持ちで迎えたくて、一生懸命自分のできることをこなしてきたのに結果がついてこない。もう半場やけくそだった。今日何度目かのため息をつく。
でも卒業式前日にこの精神状態は不味いと思い直した。
鬱屈とした気分を晴らすべく、噓八百並べたお行儀の良い履歴書をびりっびりに破り捨てた後、思いっきりそれらを踏みつけてやる。
それからグリムとゴーストを誘って面白い映画を見て笑い転げ、トランプやゲームもした。とっておきのツナ缶も開けて、オンボロ寮でささやかな卒業パーティーをした。
すると、なんだか胸がスカッとしてきて自然と笑みがこぼれ、もう将来のことなんてどうでもよくなった。ケラケラと笑う私に、ゴーストとグリムが顔を見合わせる。
そのとき、初めてぽつりと溢したグリムの言葉を、私は今でも覚えている。
「お前なら大丈夫なんだゾ、この大魔法使いのグリム様もいるしエースやデュースもいる」
「一人じゃないんだゾ! その……だ、だから大変な時は力になってやってもいいんだゾ!」
「そうじゃ、ユウ」
「ワシらは実体はないし頼りないかもしれないが、話を聞いてやることくらいはできる」
「いつでも頼っていいんだよ」
グリムやゴーストたちが安堵した表情を浮かべていたから、私はその時初めて自分の姿をまじまじと鏡で見た。目の下には濃い隈ができていたし、少し痩せた気がする。最近ではため息ばかりついていた。傍から見れば、相当やつれていたのかもしれない。
グリムたちの気遣う眼差しも、言葉も、何もかもが温かくて優しくて。私はこの世界に来てから初めて泣いた。大粒の涙が瞳からこぼれて止まらなかった。卒業式前日だというのに、大泣きした。しゃっくり上げて泣き出した私にグリムはおろおろしていたし、ゴーストたちは寄り添って頭を撫でてくれた。みんなに慰められて、優しい言葉に包まれて、心の乾いた部分が幸福感に満ちていくのを感じた。私は自分が孤独を感じていたのだと、ようやく実感したのだった。
そうして迎えた卒業式当日、ゴーストやグリムの介抱のおかげで泣きはらした目元を晒さずに済んだ。少し目が充血していたけれど、目元の腫れは随分とマシになったので上手い具合に化粧で粗は誤魔化してしまった。結果として私は何の成果もないが、爽やかな気持ちで式に臨むこととなった。隣に立つ小さな暴れん坊将軍ことグリムが、いつの間にか頼もしい味方として成長し、とうとう同じく卒業すると思うと、なんだか感慨深いと同時に誇らしい気分だ。
式が終わり、同学年の生徒と写真を撮ったり、最後の談笑に花を咲かせていた。
誰かが声を上げたのをきっかけに、周囲の生徒たちがどよめき出す。
「おい、あれって……」
「なんで……ここに?」
「来賓で来てたとか?」
何だろうと思って、周りと同様にきょろきょろ辺りを見回す。
ふと影が頭上に落ちて、反射的に顔を上げた。
瞬間、息を吞む。ヘテロクロミアの双眸と視線がかち合う。
一瞬、時が止まったかのような感覚に陥った。
気まぐれに吹いた風がふわりと香水の香りを運び、鼻先を掠める。監督生好みの香りだが、恐らく男性ものだろう。爽やかな香りの中にひっそりと甘さが漂っていた。
ターコイズブルーに一房垂れた黒い髪を持つ、高身長の特徴的な容姿。
私の見立てが確かなら、彼は一年前に卒業したジェイド・リーチだ。
何故ここにいるのかと、疑問が浮かぶ。ジェイドはフリーズしてぎょっとした様子の私を、しげしげと一瞥した。そして口元にゆるりと笑みを湛える。
「お久しぶりです、監督生さん」
「は、はぁ……どうも、お久しぶりです」
「まずはご卒業、おめでとうございます」
驚きで未だ現状を把握できない私をよそに、彼は懐かし気に辺りを見回す。
すぐに満足したのか、こちらに流し目で視線を寄こした。
また背が伸びたのかもしれない。見ない間に随分とこの一年で大人っぽくなったな、と思う。いかにも質の良さそうなスーツスタイルで、かっちりと着込んでいる。髪も軽くセットされて、学生の時とは違う雰囲気だ。花束まで抱えて、一体全体何の用事でこんな辺鄙なところにまで訪れたのだろう。
かつて相対したオクタヴィネル寮の寮長、アズール・アーシェングロットは卒業後、数年足らずで起業した。今や若手敏腕社長として雑誌、テレビで、日夜注目の的である。勿論、その隣にはあの頃と変わらず、フロイドとジェイドが後ろに控えていた。
三人とも、戦略のみならず、外面の良さと巧みな話術、なにより美しい容姿からよく目立っていた。この世界の情勢に疎い私でも、スマートフォンのニュースや雑誌の一面を飾る彼らを見たこと、一度や二度ではない。そんな多忙な彼が何故かここにいる。
周りの生徒たちが騒めいても、仕方ないというものだった。
「ありがとうございます……あの、ところで何故こちらに?」
「ああ、そのことなのですが────」
よくぞ聞いてくれたといった様子で胸の前で柔らかく手を添え、フッと微笑む。
「────あなたに折り入ってお話がありまして」
ジェイドは少し身をこちらに屈めると、極めつけに見事な営業スマイルでにっこりと笑んだ。この時点でかなり胡散臭い。しかし何も聞かずに「結構です、お帰り下さい」と言うほど、監督生も薄情ではなかった。仮にも共に学び、一悶着あり、和解した(?)仲だったので。
であるからして、ユウは当たり障りのない返事でのらりくらりと躱しつつ、本音を探ることにした。
「はぁ……私に?」
「ええ、少し長くなるので、良ければオンボロ寮にお邪魔させて頂いても?」
「それはいいですけど……これから友人たちと写真を撮ったりするので、しばらくお待ちいただくことになりますよ」
「構いませんよ、いくらでも待ちます」
腹の内は探りきれず、何やら話が長引きそうな気配だ。正直、面倒くさい気持ちが勝っている。 しかし彼の根気強さとしつこさは、尋常ではない。この身で体験したことのある私だからこそ、さっさと要件を聞いておいた方がいいだろうと思い直す。
「ん~……それなら先に、オンボロ寮で待ってていただけますか?」
「わかりました。 最後の機会ですし、ゆっくりご友人とお話されてください」
「僕は、急ぎませんから」
にっこりと貼り付けられた笑みの裏は、何を思っているのか。
やはり、引く気はなさそうだ。どう足掻いても要件を終えるまで、私を逃がす気はないらしい。時には諦めも肝心なのだろう。長い人生の中では。
ここで大人しく用件を聞くことにして「では、お言葉に甘えて……また後ほど」と軽く会釈する。
ジェイドは去り行く彼女の小さい背中をしばらく見つめていたが、ゆっくりと踵を返した。
周囲の動揺もその頃には収まり、生徒たちの関心は他のことに移っている。
「ごめん、お待たせ! それじゃ、みんなで写真撮ろっか」
「遅いぞ! いつまで待たせるんだ、ユウ!」
「ごめんって、ちょっと先輩に捕まってて……」
小走りで駆け寄ると、セベクが抗議の意を唱える。
色々あって、彼は人間呼びを滅多にしなくなった。セベクも成長したのだろう。入学当初は名前なんて覚えていないし、とにかく当たり屋のようだった。
それが今では、ちゃんと個々に対して向き合うようになった。実に喜ばしい限りである。
……まぁ、声量は相変わらずだが。
「まぁまぁ……セベククン、最後なんだから穏やかに、ね?」
「お前だって上級生に呼ばれたら、急いでても返事するだろ」
エペルとジャックが宥めると、彼はぐっと堪えるような顔をする。
痛いところを突かれたようだ。
「そーそー、例えばリリア先輩とかさぁ」
エースもニヤリと意地の悪い顔で、追い打ちをかける。
「当たり前だ! マレウス様やリリア様より優先すべきことなどない!」
「お、おう。 そうだよな! 頭を敬う気持ちはわかるぞ!」
「デュース、おめェそういうことじゃねーんだゾ」
頓珍漢なデュースの励ましに、呆れるグリム。
何もかもが日常で繰り広げられてきたことばかり。
これから先はこの日々が思い出に変わっていくのだと思うと、少し寂しい気持ちになる。
「んじゃ、撮りますか~……ほい、集まれ~」
エースが集合をかけると、一斉にいつものメンバーが周りに集まる。
セベクだけが取り残されると、慌てて駆け寄ってくる。それにエペルとユウは顔を見合わせて笑った。
「おい、なんだ! その不敬な態度と言葉は!」
「それじゃ、撮りますよー」
もはや対セベク用スルースキルを身につけたユウたちに怖いものはない。
エペルはにっこり笑うと、セベクに笑みを促す。
「セベククン、こんな時くらい怖い顔はナシ、だよ」
「……む……そ、そうだな」
「はい、いくぞー……さん、にー……いち」
パシャ……パシャ……
冬の青空に、生徒たちの賑やかな声が響き渡る。
はしゃぐ卒業生たちの喧騒の中で、今でも鼓膜にあの時のシャッター音が鮮明に響く。
式典服に身を包んだ学友たちと、全員で変顔やポーズをキメて撮った写真は今でも私の宝物だ。最高に最悪な日もあったけれど、ハプニングさえ今では愛おしい。
振り返れば、素晴らしく青春だったと思う。
●
「お待たせしました……すみません、遅くなって」
陽も傾き始めた頃ようやく帰路に着いたユウは、オンボロ寮の談話室で待つジェイドに声をかけた。想像以上に遅くなってしまい、謝罪の言葉を述べる。
ほぼ沈みかけた夕日を、彼は窓辺の席で静かに見つめていた。ユウの声が聞こえるとスッと顔をこちらに向ける。ゆったりとした微笑みを浮かべるジェイドの表情は、まるで絵画や彫刻のように美しかった。
「いえ……この程度、どうということはありませんよ」
彼は穏やかな口調でそう言うと、ユウに座るよう仕草で勧めた。
お言葉に甘えてソファに腰掛けると、暖炉の火がパチパチと爆ぜていることに気付く。
「あったかい……」
「外は随分と冷えていたので、念のため暖めておきました」
気が利くところは相変わらずのようで、ユウは懐かしさに頬が緩む。
「流石ですね、ありがとうございます」
「勝手なことをしましたが、ご迷惑でなくて良かったです」
「いえ、そんな……助かります」
ジェイドは胸の前に手を添えると、微笑んだ。
学生時代、モストロ・ラウンジで従事していた頃のような振舞だった。顧客の意に添えたことを嬉しく思う表情を浮かべる。
「あの……つかぬことを伺いますが、今日はお仕事なのでは?」
はたと気づいて、気になっていたことを訊ねると「有休を使いましたので、ご心配なく」と返事を返した。まさか仕事を放ってわざわざ在校生の卒業式に来るようなタイプではないし、不思議に思いつつも「そうですか」と頷いておく。ささっと手早く用件を聞く作戦は使えなさそうだった。
「ええ、ですので慌てなくても大丈夫ですよ」
まるでこちらの思考を読み取ったような返答に苦笑する。
ふと、視界に映ったのは窓辺に飾られた花束。
それは先程、彼が持参していた花束だった。何故、それがオンボロ寮の花瓶に活けられ、置かれているのか疑問に思う。
「これって、さっきの花束ですよね?」
「はい、あなたに」
「私にですか?」
内心、訝しむ。
驚きを隠せずにいると、彼は可笑しそうに「他に誰に渡すんです?」と訊ね返す。それにうーんと唸って思案する。
「学園長、とか……?」
人差し指を立てて、思い浮かんだ人物の名を上げる。この学園で一応、一番偉いのはあの人だろう。堪らずとうとう我慢できないという様子で、彼は口元に手を添えて笑った。
「んふっふ、本当に飽きない人だ」
「……はぁ、どうも?」
「最初から、あなたに贈ろうと思って持ってきました」
「そうなんですか……? なんだかよくわかりませんが、ありがとうございます」
未だ信じられないことだが、一応礼を言う。
全くもって、腹の底が読めない男である。
そんな私の失礼な考えなど知らずに(もしくはわかっていて意に介していないのか)、彼は机の上に置かれていた紙袋から箱を取り出し、中を見せるようにこちらに差しだす。
艶々とベリーが輝くフルーツタルト、王道のショートケーキ、栗の衣を惜しげもなくふわふわと纏ったモンブラン、南国の香り漂うムースケーキ。
いかにも美味しそうな、見栄えのよいケーキが揃ってこちらを誘惑してくる。
ごくりと喉が鳴るのも致し方ないことだろう。
「手土産のケーキがありますが、いかがですか?」
ユウが首を縦に振らないことなど有り得ないのに、彼は形だけは訊ねてくる。
何とも意地の悪いことであるが、今の私には関係ないことだった。眼前の美味なるケーキを前にして文句を言う気も、はたまた断る理由もない。ユウはやや食い気味に瞳を輝かせて頷いた。
「とっても美味しそうですね……頂きます!」
「……ふふ、花より団子とは、このことですね」
ジェイドは満足そうに頷くと、くすくすと笑った。
「今、ちょっと失礼なことを言われた気がする……」
「いえ、聞き間違いでしょう……ところで、キッチンをお借りしても?」
「構いませんが……何か要りますか?」
上手く誤魔化された気がするが、ケーキのためだ仕方ない。ヒトは食の欲求の前に無力だ。
学生時代、何度も他の生徒たちとオンボロ寮に訪れただけあり、彼は勝手知ったるとばかりにキッチンに向かう。その背を追いかけると、振り向いたジェイドが静かに片手で制した。
「紅茶を淹れてきますから、少しお待ちいただけますか?」
「あ、それなら私も手伝いますよ」
紅茶の淹れ方で彼に敵うはずもないが、私だってお湯くらいなら沸かせる。先程から頂いてばかりで申し訳ないし手伝わせてほしい、と付け加えれば彼は困ったように微笑んだ。
「ありがたい申し出ですが、今日はもてなしたい気分なんです」
幼子に語り掛けるような優しい口調だった。
今まで聞いたことのない声色に、思わず身体が強張る。
「……良い子で、待っててくださいますよね?」
「あ、はい……」
「ありがとうございます、腕によりをかけますね」
懇願するような言葉と有無を言わせない雰囲気に押されて、思わず頷いてしまった。再びソファに腰掛けると、ソワソワと落ち着かない気分で彼の用意が整うのを待った。
パチパチと時折、暖炉から火が爆ぜる音が聞こえてくる。
そうしてしばらく手持無沙汰な状態の私は、暖かなオレンジ色が揺らめくそれに見入っていた。
「お待たせしました」
背後から声がして、ジェイドが茶器とティーポットを机に置く。
「何から何まで、ありがとうございます」
「いえ、僕が好きでしたことですので……ところで、どのケーキがいいですか?」
「私から選んでもいいんですか?」
「勿論です、あなたのために用意したんですから」
「じゃ、じゃあ……」
それからは至れり尽くせりで、文字通りもてなされることとなった。
「えー……それで、あの、私に用事があったそうですが……ご用件は?」
こほん、とわざとらしく咳をする。彼の方を向くと、居住まいを正した。
いたくもてなされてしまい、ケーキも美味しくて完全に失念していた。彼は私に何か用事があったらしい。卒業式後で気分がハイになっていたこともあり、ついつい普通に楽しんでしまった。久しぶりの再会ということもあり話が思いの外、弾んだことも原因の一つではある。
ジェイドは微笑みを浮かべたままだ。その言葉に茶器を机に置くと、そっと膝の上で手を重ねる。ただ膝の上で手を重ねただけなのに、ジェイドがすると非常に洗練された所作に見えるから不思議だ。
「単刀直入に申し上げると────」
一呼吸置いた。どんな無理難題が降り掛かってきてもおかしくはない。
身を固くしてあからさまに緊張する私を、彼はクスリと笑みを深めてじっと見つめる。
まるで猫に捕食される前の、鼠のような心地だった。
「────実はかねてより、あなたをお慕いしておりました」
あまりにするりと事も無げに伝えられる。どうやら、それは告白だった。
しかも、よりにもよって私が対象らしい。彼の口からそんな甘やかで穏やかな言葉が出るなんて、物騒なリーチのヤバイ方であるジェイドには、似つかわしくない。
いや、確かに……もう子供ではないのだから、恋の一つや二つあってもおかしくない。
だけど、なぜわざわざ私に?
学生時代からなかなかの曲者だったが、とうとうそのお綺麗な容姿を武器に恋愛詐欺師になったのだろうか。だとしても、相手を選ぶだろう。
何も持ち得ない私をいたぶっても、一銭だって出やしないのに。
「ええ、ですからこうして迎えに来たわけです」
「あの、話が跳躍しすぎじゃないでしょうか? え、うん……迎えに来た?」
「はい、僕からすれば随分と待ちましたから」
彼の話についていけず、眉を顰めて首を捻る。
怪しい、怪しすぎる。全然、意味が分からない。
「あなたが卒業するのを待っていました、ずっと」
「……」
何も言えずに紅茶をちびちびと啜る。とにかく、冷静にならなければいけない。
とっくの昔に冷めてしまった飴色の液体は、するすると喉を嚥下する。
「他の男に目移りする可能性もありましたが……慎重なあなたのことだから、きっと恋に現を抜かすことはないと踏みました」
「……そうですね、確かにそんな暇はありませんでしたから」
「そうでしょう? ふふ、読みが当たって良かったです」
この男の読み通りになったことが、なんだか癪だ。
ジェイドは上機嫌に手を組み替える。
「あなたはこの世界に痕跡を、爪跡を残すことを良しとしない」
「それはご自身のためでもあり、同時に周囲のためでもある」
「違いますか?」
とうとうと語りかけるジェイドの言葉は、痛いほど的を得ている。
それはユウが最低限身に着けた処世術であったし、明確な線引きだった。
誰も傷つけたくないし、自分も傷つきたくない。元の世界に帰れる望みがあるうちは、絶対にその線引きを緩めなかった。
それで例え、卑怯者、臆病者と言われようと結構だった。
責めるような口調でもないのに、妙に居心地が悪い。あまりにも敏いこの男が今は心底恨めしいし、気味が悪かった。
「……何でもお見通しなんですね」
「いえ、僕にもわからないことはありますよ」
ジェイドは目を伏せて、小さく抗議する。
「例えば、あなたの本心」
「そこまで見透かしておいて、よく言いますね」
なんと白々しい、呆れてため息をつく。
しかし彼は至って真面目な顔つきでこちらを見据える。
「あなたが頷いてくださらないと、今日の徒労も無駄足になる」
「僕はずっと、あなたを慕っていた。 けれどあなたは、気付いていなかったでしょう?」
「はい、ジェイド先輩は特に自分の感情を悟らせないのがお上手でしょう?」
「あんなにアプローチしていたのに、気づいてもらえないなんて心外です、しくしく」
「それで……結局、告白しに来ただけですか?」
「いえ、ご提案をお持ちしました」
彼の言葉を躱しつつ、返答はノーだと態度で示す。
あえていつもより冷たい言葉を投げかけても、ジェイドは全く取り合わなかった。
オクタヴィネル寮元副寮長の提案なんて、考えるだけでも恐ろしい。今度こそ、きっぱりと断るつもりで断固拒否の姿勢を示す。
「取引なら間に合ってます」
「まぁ、そう言わずに。 聞くだけならタダですから」
「はぁ……嫌な予感……」
強引なのは相変わらずのようで、彼は人の返事を聞かずに話の続きを口にする。
「僕は今、一軒家に住んでいるのですが、かなり広いんです」
「はぁ」
「ご存じの通り事業も軌道に乗っているので、お金には困っていません」
「でしょうね」
「あなたは就職されると風の噂でお聞きしましたが……もう内定を?」
どこまでも目敏く、そして情報網が広いことだ。
痛いところを突かれて、項垂れつつ片手を上げる。
「いえ、さっぱりです。 惨敗でした」
「となれば、話は早い」
「僕の家に来ませんか?」
ジェイドはにっこりと笑みを浮かべた。
お得意の営業スマイルだ。これがそこら辺の令嬢やうら若き乙女なら、この時点ですでに彼に落ちていただろう。
しかし、監督生はこの男もとい人魚の性質も性分も、学生時代に嫌というほど身をもって知っていた。ちょっとやそっとじゃ、靡くはずもない。彼の言葉にあからさま、顔を顰める。そして、都合の良い方向に解釈しようとした。
「シェアハウスってことですか?」
「いえ、同棲です」
「同棲……」
期待むなしく、彼女の望みは儚く散っていった。
ジェイドはなおも笑みを崩さない。
「はい、先程申し上げた通りお金には困っていません。 ですので家賃や生活費はタダで結構です」
「その代わり、と言っては何ですが……僕と共に暮らしていただければ」
「勿論、あなたの了承なしに身体に触れたり、過度な接触は致しません」
ジェイドの提案はまさに理想、願ってもないほど好条件だった。あまりにも私に都合がよすぎて、耳を疑うレベルだ。これはきっと裏があるに違いないと、探りを入れる。
「……それはあまりにも、私に都合が良すぎる話ですね」
「ふふ、そうでしょうか?」
彼はギザギザの歯を隠すように口元に手を添える。
「よく考えてみて」
まるで催眠術をかけるかのような穏やかでしっとりとした声色は、ユウの鼓膜を揺らす。
彼はそっと立ち上がり、彼女の近くに歩み寄った。そうして大して綺麗でもない木の床に、片膝をついてユウを見上げる。
「僕は好いた相手を手元に置いておける上に、共に暮らせます」
労るように、両の手を彼の手のひらが包み込む。自分よりもずいぶん大きい掌に、途端冷や汗が出る。今、彼の機嫌を損ねれば、一瞬で骨を折られる気がしたからだ。ジェイドの指先はしなやかで、自分よりもいくらかごつごつとしている。そしてユウよりもいくらか冷たかった。
「あなたの自由を、時間を独占し、奪うことになります」
「そう考えれば、妥当では?」
小首を傾げる彼に、私は苦笑した。
想像以上に熱烈な想いをぶつけられて、どう反応するのが最適解か皆目見当もつかない。
「うーん、こればっかりは価値観の違いですね」
「そうですね、僕にとっては何より価値があるのですが……」
「うーん……でも悪いなぁ」
「何がです?」
キョトンとするジェイドに、唯一引っ掛かりを覚えている事柄について意見する。
「先輩に全てお金を出してもらって、その上衣食住を与えられるなんて……ちょっと引け目を感じますね」
「もし気になるようでしたら、少し家事を手伝って頂ければ助かりますが」
ジェイドの言い分に私はまた苦笑した。まったく釣り合いが取れていない。これが当時、手心なしと恐れられていた、オクタヴィネル寮のジェイド・リーチとは思えなかった。
「どうでしょうか? 悪くない話だと思いますが……」
「ジェイド先輩のことを好きになる保証は、どこにもないですよ?」
「それでもいいんです、傍にいてくれさえすれば」
「一生、同居人止まりでも?」
「ええ、寂しいですが……それでも構いません」
ほんの一瞬、悲しそうに微笑んで、彼は静かに頷いた。
切なげな瞳で見つめられて、息が詰まる。
「ジェイド先輩の本音なんて珍しい……」
「それくらい、必死ということですよ」
「……」
「来てくださいますか?」
彼の指先が僅かに震えている。包みこむ指先に僅かに力がこもった。
乞うような眼差しを向けられて、どきりとする。これがもしも全て、私を誘惑するための計算に入っている仕草なら、彼はプロの詐欺師だと思う。
しかし、真摯な眼差しに耐え切れなくなったのは、紛れもなく私の方で。
──────もし、嘘だとして……それでも騙されてもいいかな、と思ってしまった。
ため息を吐いて、私は彼の手をほんの少しだけ握り返す。
「…………そうですね、正直願ってもないほどの好条件ですし、お受けします」
「ほんとですか……!」
途端、水を得た魚のように先ほどまでのしおらしさは消え失せ、飛び掛からん勢いで抱きしめられる。ぎゅうぎゅうと抱き込まれて、息が苦しい。おまけにいい香りがして頭がクラクラする。
極めつけは右頬に軽く唇が触れて、リップ音が響いた。
「わ、ちょ、……許可なく触れないんじゃ……なかったんですか?」
「今日だけは大目に見てください! 僕とても嬉しくて歯止めが効きません!」
「わわっ、ちょっと! もう、ふふふ、あはは、じゃれつく大型犬みたい」
「犬になった覚えはありませんが、今ならなんにでもなれそうです」
オンボロ寮の談話室にはたった二人しかいないのに、まるでパーティーのような賑わいだったと後にゴーストは語る。
かくして彼女、オンボロ寮の監督生ユウは、少ない荷物とともにこの学園を去っていった。
まだ春にもなり切れない、冬も終わりかけの寒い時期だった。
●
午前0時を過ぎても、彼からの連絡はなかった。
待つ間にもスマートフォンに何度か通知が入ったが、それら全てはどうでもいいニュースやトレンドの広告だ。開くまでもなく、すぐに消去ボタンを押す。
ソファに座り、軽めのブランケットを羽織って温かいハーブティーを一口飲む。適当につけたテレビを見るのも飽きてきた。
「こんなこと、滅多にないのに……」と、軽く首を傾げながら独り言ちる。
彼の家に同居するにあたり、初めに二人でいくつかルールを決めた。
そのうちの一つに、門限は午前0時、その時間を過ぎるときは必ず連絡すること。そういう項目がある。
その日は普段マメな彼にしては珍しく、何の連絡もなかった。きっと仕事が忙しかったのだろう。本当に時々、あまりにも忙しいと連絡する間もない日がある。連絡がなかったからと言って怒ったりしないが、少しだけ気になるのも事実だった。
ユウが連絡もなく帰りが遅くなるときなど、それはそれは静かにキレるので後が怖い。ネチネチと長引くジェイドのお小言は、可能な限り回避したいのだ。それ故、ユウはどんなときでも連絡だけは欠かさずにしていた。
それなのに、自分はいいのか……と内心もやもやとした気持ちを抱える。
うつらうつらとし始めて、伸びをした。そろそろ先に寝てしまおうか。そう思った矢先、玄関から控えめな開錠の音がする。眠い目を擦って、よたよたとそちらに向かう。
こちらの姿に気づくと、困ったような笑みを浮かべたジェイドは「ただいま帰りました」とばつが悪そうに口にした。
「おかえりなさい、ジェイドさん」
「遅くなって申し訳ありません」
「いえいえ、お仕事お疲れ様です」
欠伸を噛み殺しながら、返事をすれば愛しそうに目を細めて頬に触れられる。
まぁ、これくらいの触れ合いならいいか、と大目に見て、彼の瞳を見つめ返した。
「ずっと……待っていたのですか?」
「待ってたと言っても、ご飯もお風呂も先に済ませましたよ?」
申し訳なさそうにするジェイドに、微笑んでみせる。
彼は大きなため息を吐くと、もう一度小さく「すみません」と謝った。
「気にしないで下さい、お忙しいかと思って……もう少ししたら、寝るつもりでした」
「今度からは気を付けますね」
「ふふ、構いませんよ。 ごはん温めますね」
「はい、ありがとうございます」
「先にシャワーでも浴びててください」
私は彼のジャケットを預かると、そのまま衣装棚のハンガーにかける。
そして台所に向かうと、用意していたスープとおかずを温めにかかった。
こんな穏やかな日々がこの先も続けばいいのに、と願いながら。
●
「で、どうよ? ジェイド先輩との生活は?」
開口一番、久々の再会もそこそこに、エースの発言である。
三人の仕事が忙しくて、半年ぶりにランチをしている最中のことであった。以前より随分と顔つきが大人びたエースとデュースは、体格も大きくなって大人の男性になった。学生時代のあどけなさは、もうあまりない。グリムもすっかり魔法士としての仕事が板について、ちょっと賢げに見える。
容姿も能力も、大して変わらない私とは大違いだ。
自分を取り囲む周囲との年月の差を思い知らされるようで、少し寂しく思っているのは内緒だ。
「うーん、どうよって言われてもなぁ……」
「僕も心配してたんだ、酷いこととかされてないか?」
「オレ様、子分はもう少し見る目があると思ってたんだゾ」
「あはは、ひどい言われよう」
成人男性三人の胃袋を鑑みて(約一名、魔獣だが)、バイキング形式のレストランに予約してよかったとつくづく思う。
お皿にこれでもかと盛られた山盛りの料理やケーキに、本当に胃袋に入るのかと最初は疑惑の目を向けたが、もう既に半分ほどに減っている。恐るべし、食べ盛りの胃袋である。
とはいえ彼との生活を思い浮かべてみると、特別なことは何もないが、かといって大変なこともない。過度な接触もないし、嫌がることは何もされていない。家事は大半をこなしているが、それに不満はない。それに休日には率先して掃除・洗濯・食器洗いをこなしてくれるし、重い荷物も持ってくれる……考えても至れり尽くせりすぎて、笑ってしまいそうになった。
「失礼だけど、疑わない方が無理はあるよな……」
「でもさ、あんだけ執着されてて、気づかないユウもユウだけどな」
デュースは未だにイソギンチャク事件の恐怖を忘れていないらしく、首を捻った。それに頷きつつ、神妙な顔でエースはこちらを一瞥するとチェリーパイの欠片を口に放り込む。
「いや、私も色々考えてみたけど、そんな要素一ミリもなかった気がするんだよなぁ」
「確かにな。 同棲するって聞いた時は、いきなり過ぎて僕も正直びっくりしたぞ」
「いやいやいや、二人揃ってほんっと鈍感すぎ!」
「そうか……?」
「そうかなぁ……?」
「……オレ様はオクタヴィネル寮の奴らと一緒に暮らすなんて、絶対に御免なんだゾ」
それまで食べることに夢中だったグリムが口を開くと、興味なさげにぼそりと呟く。グリムにすれば、恋や愛など腹の足しにもならない事柄は、どうでもいいのだろう。
「そう言えばエースは彼女さんと上手くいってるの?」
「まぁなー、今度一緒に物件見に行こうって話てるぜ」
「そっかそっか、いい物件見つかるといいね」
「エースもその、ど、同棲するのか?」
「多分な」
それまで口いっぱいにおかずを頬張っていたデュースが、気恥ずかしそうに訊ねる。
私もこの手の話題には疎いが、デュースはもっと免疫がない。
自分のことでもないのに、既に緊張の面持ちで真剣にエースの話を聞いている。
「そういうデュースくんはどうよ? ちょっとは気になるあの子と進展あった?」
「あ、グリム、このケーキ美味しいよ」
「えっっ……ぁ、あったような……なかったような……」
「ふな! 子分これもうまいぞ! 特別に一口分けてやる」
「ありがとう、私のも一口どうぞ」
ニヤニヤと人の悪い笑みを浮かべるエースに、デュースは途端カチコチと挙動不審になる。頬が赤く染まり、しどろもどろに発言する様子は微笑ましい。最後の方は声が尻すぼみになって、ほとんど聞き取れなかった。
グリムと一口ずつケーキ交換をしながら、その様子を観察する。
こうしていると、学生時代に戻ったような気がした。
「そっかそっか、デュースくんにはまだ早かったでちゅね~」
「ば、馬鹿にするなよ! 僕だってやるときはやるんだからな!」
「その割には、なかなか進展ないよなー」
「ぐっっ……」
デュースは真っ赤な顔で、鼻息荒く抗議の意を唱える
それを宥めながら、私は「そう言えば」と話を切り出した。
それに気づいた三人がこちらを向くと、私はニヤリと笑みを浮かべる。
「……進展というか、ひとつ面白いことがあったよ」
「お、なになに?」
「どうしんだ?」
彼らの期待の眼差しに、私は名探偵のような気分になる。
「ふっふっふ、聞いて驚け~」と陽気に口にすると、どや顔で先日のことを報告する。
「ジェイドさんのシャツ、襟元に口紅のシミがあったの」
「「え……」」
顔を引き攣らせる二人に、私はため息をついて両手を上げる。
やれやれだ、というように。
「浮気一つにしてもさ、もっとスマートにする人だと思ってたから、ちょっとガッカリだけどね」
「気にするところ、そこ?」
「……子分、その話笑いにくいんだゾ」
「グリムと珍しく意見があったわ」
「それ、大丈夫なのか?」
「今のところは大丈夫だね、生活費も貰ってるし」
呆れるエースとグリムの視線を躱しつつ、デュースの気遣わし気な眼差しにきっぱりと頷く。本当にこれといってなにも困っていないのが、自分でも不思議なくらいだった。ストローでトロピカルな色合いのジュースを啜ったエースは、一気に疲れた様子で首を横に緩く振る。
「お前さぁー……たまに冷静過ぎて怖いわ」
「ふふ、なんかテンプレみたいな展開で、ちょっとワクワクしてて」
「そこは落ち込むのが普通だぞ、ユウ」
「安心して! ちゃんと備えはあるから!」
想像の斜め上を行くユウの考え方と行動力に、デュースまでもが真剣に呆れている。
今日一番の大きなため息を吐くと、エースは気だるげにひらひらと片手を上げた。
「はぁー……何かあったら連絡しろよなー」
「何があっても僕たちは、監督生の味方だからな!」
「まぁ、子分をいじめる奴は、親分がとっちめてやるから安心するんだゾ」
「みんなありがとね、いざとなったら頼りにしてるよ」
なんだかんだ言って優しいマブと親分に背中を押され、上機嫌で頷く。
なんとか着地地点を見つけたこの話題は一旦休題となり、話題はエペル、ジャック、セベク、オルトのことへと変化していった。マジカメのアカウントで繋がっているため、近況はなんとなしに知っている。けれどやはり直に会って話したいなとのことで、後日会うことに決めて、話はとんとん拍子に進んでいった。
楽しい時間はあっという間に過ぎていく。
外の街路樹は紅葉を迎え始め、もうすぐ本格的な秋が来るだろう。
私がツイステッドワンダーランドに来てから、十回目の冬を迎えようとしていた。
●
午前一時。午前二時。午前三時。
ジェイドはその日、帰ってこなかった。
ちょっと気になって一言だけ「遅くなりそうですか?」とメッセージを入れてみた。しかし、既読すらつかない。
電話をかけてみようかとも思ったが、それも仕事中だったら申し訳ないと躊躇われた。それにお互い束縛はしないルールだ。これも共に住むにあたって決めた約束事だった。過度に心配するのはよそう。重たい腰を上げて、居間から自身の寝室へ向かう。
久しぶりにこんな遅くまで起きていたので、流石に眠い。
ジェイドとユウの寝室は別室だ。その為、お互い気兼ねなく好きな時間に眠っている。
ただ、いつも交わしている「おやすみなさい」の挨拶がないだけで、随分と感じ方が違うものだな、と思う。寂しいとは違うが、なんだかしっくりこないのだ。
冷え切った寝室のベッドに横たわり、羽毛の布団とブランケットをかける。じんわりと徐々にぬくもりが広がって、眠りに誘われた。
「遅くなります」の一言があれば、気にすることもないのだ。あんなにマメだった人が、ぱたりと連絡をよこさないというのは、やはり浮気なのかもしれない。うとうとと微睡む意識の中で、私は掠れた声で口ずさむ。
「二回目」
瞼の裏で、ターコイズブルーが揺れた気がした。
翌朝、いつもより遅い時間に目を覚ます。
微かな物音が一階から聞こえて、彼がいるのだと気づく。
二階の寝室から一階の居間に降りると、やはりキッチンに見慣れた姿が立っていた。
お湯がシューシューと沸いて、茶器がかちゃりと小さく音を立てて置かれる。テーブルには、二つの茶器が用意されていた。
いつも時間のある時は、何も言わなくとも二人分の紅茶を用意してくれる。
その何気ない気遣いが私は好きだ。こういう些細なことに幸せを感じるのは、何も私が変わっているからではないだろう。
「おはようございます、ジェイドさん」
「おはようございます、ユウさん」
寝間着姿の彼は少しだけ、いつもより幼く見える。
穏やかな眼差しがこちらに向けられて、私はくすぐったい気持ちで傍に歩み寄る。
「昨夜は遅かったみたいですが、いつ頃帰られたんですか?」
「仕事が長引きまして、明け方に」
「大変ですね、お仕事お疲れ様です」
いつものように労いの言葉をかければ、彼は困ったように微笑んだ。
ほんの僅かにぎこちない、歪な微笑みだった。もう何年も共に暮らしているからか、彼の表情の機微に気付けるようになった。
果たしてそれが良いのか悪いのか……私には判断がつかない。
「今日は昼から出社してもいいので、少しゆっくりしてから行こうかと」
「そうなんですね、少しでも休めるならよかった」
「あの、ユウさん……」
「なんでしょう?」
ジェイドは言いづらそうに、おずおずと会話を切り出す。
決まりが悪そうに、湯気の立つ茶器をこちらに差し出した。それを両手で受け取ると、口元に傾ける。飴色の液体が甘い香りと風味を伴って、舌先に残っていく。
今日はキャラメルのフレーバーティーらしい。
「昨夜……連絡できずに、すみませんでした」
いつになくしおらしい様子に驚きつつ、首を横に振る。
決して責めたいわけではないのだと、表情を硬くする彼に伝える。
幾らか緊張が和らいだジェイドに、こちらも安堵して微笑んでみる。
「いいんですよ、ジェイドさんが無事で何よりです」
「……本当に、物わかりの良い方だ」
何かを耐え忍ぶかのような表情に、私はそっと彼の頬に手を伸ばす。ジェイドは吸い寄せられるようにそっと、こちらに身を屈めた。彼の頬に指先が触れる。陶器のように滑らかな質感だった。親指の腹で優しく表面を撫でれば、心地よさそうにそっと瞼を閉じる。
何かを悔いるような表情に、私は再度首を横に緩く振る。
「大人なんだから、そんな時もありますよ」
「ユウさん……」
「あまり気に病まないでくださいね」
彼の片手が頬に触れる私の手を掴んで、もっととせがむ様にすり寄ってくる。
自分よりも高身長の成人男性が甘える様子は、なんだか可愛らしく映った。
この時はまだ、穏やかに過ぎていく日々に忍び寄る影を知る由もない。
●
────本当は、明け方に帰った訳ではなかった。
仕事だって、言うほど忙しくはない。それでも遅くに帰った。いつもより、うんと遅くに。
こんな時間に帰宅するのは、いつぶりだろう。
彼女と暮らすようになってから、できるだけ早く帰ろうと努めていた。少しでも長く、彼女とともに過ごしたかった。それなのに、何故自分はこんなことをしているのかといえば、それに理由はあれど、到底納得してもらえる内容ではなかった。
大きく息をついて、己の醜さに見ないふりをした。頭を左右に振って、気持ちを切り替える。
音をたてないように、静かに鍵を開けて家に入った。まだ部屋の中は温かく、温度が残っている。健気なあの子のことだから、自分を待っていたのだろう。
それが堪らなく嬉しくて、思わず口角が緩む。そのまま足音を忍ばせて階段を上がると、彼女の寝室に続く扉に手をかける。そっと中を覗くと、未だあどけなさの残る表情で、すやすやと眠っていた。傍にそっと近づいて、彼女の寝顔を見下ろす。
途端、暗い部屋の中で自分の表情が強張っていくのがわかった。彼女の寝顔をこうやって盗み見る度、凪いだ海のように穏やかな気持ちを抱けた。どんなに疲れていても、彼女がいれば、ユウが自分に微笑んでくれただけで、疲労感など容易く消し飛んだ。
───だが、それと同時に。
いつからか堪らなく、違う感情が自分の中で芽生え始めた。
それは絶対に良くないものだった。それを許容してはならなかったし、ましてや正当化などできないものだ。だから、必死に蓋をしてきた。けれど、最近どうにも歯止めが利かない。自分の意志とは関係なく、本能がそれを求めていた。
「……ユウさん」
全く起きる気配のない彼女の頬を指先で撫でる。男性のそれとは違う、柔らかで滑らかな感触だった。ジェイドが触れて与える刺激に、擽ったそうに身を僅かに動かす。
指先が離れると、また同じように規則正しい息遣いで眠り始めた。
ああ、なんて愛らしい。
全幅の信頼をもって、ジェイドを疑うことを知らない無防備な彼女が心底愛しい。自分にだけ向けられるそれが一等、尊いものに思えてならない。
けれど……同時に憎らしい。
自分の思考に浮かんだ不自然な回答に、すぐかぶりを振る。
まただ、と思った。最近、何度も何度も同じことを反芻している。
いっそこのまま一思いに彼女の全てを攫ってしまいたい。誰にも触れられない、誰の声も届かない、そんな場所で。二人だけで過ごしたい。僕のことだけを、その瞳に映してほしい。
ぐっと喉奥に力を込めて、衝動を抑え込む。
まだ、その時期ではない。
辛抱強さには自信があったのに、最近の自分はどうにも気持ちが揺らぎそうになる。
どうか、僕のこの気持ちも願いにも、気づきませんように。
そしてこの衝動が、本能が、求めるものが悪い夢でありますように。
目が覚めたら、元通りの自分に戻っていますように……
今のジェイドには、そう祈ることしかできなかった。
●
その日は朝食の準備をしていた。
ジェイドより少し早めに起きて、身支度を軽く整えたあと、部屋のカーテンを開けていく。白っぽい冬の日差しが差し込んで、一気に部屋が明るくなっていく。この瞬間が、何気なく好きだった。
最近では寒さも段々と厳しくなってきたので、暖炉の火をつける。もうじき、部屋が徐々に温もってくるだろう。
いつものようにお湯を沸かして、二人分の紅茶を淹れた後、トースターで軽く焼いたパンとサラダ、カリカリのベーコンとゆで卵をお皿に盛って机に並べる。最近はこれがお気に入りの朝食だった。
ほどなくしてジェイドが二階から降りてくると、朝の挨拶を交わして二人とも席に座る。
ジェイドは毎朝、きちんとした出社用の格好で降りてくる。今日もアイロンの効いたシャツに、紺のスラックス。家から出る直前までは第二ボタンまで外して、少し寛ぎモードだ。二人で何気ない会話を交わしながら、ニュース番組を見る。
その時、ジェイドは首元を擦るような仕草を見せた。ちらりと覗く首筋には赤い斑点が所々に散らばっている。
「虫刺されですか?」
ふと気になって、季節外れの虫刺されに小首を傾げる。
悪気など全くなかったが、触れてほしくなかったのだろうか。
ジェイドはそれまでのにこやかな表情を一瞬、硬くした。
隠すように、シャツのボタンを最後まで閉じてしまう。
「……ええ、そうみたいですね」
「痒いですか?」
「まぁまぁです」
貼り付けたような笑みに、違和感を感じた。
彼のまぁまぁ、はあまり当てにならない。以前、それを鵜呑みにして放っておいたら、風邪が悪化して大変だったのだ。食べる手を止めると私は立ち上がり、薬箱の棚に手をかける。
「塗り薬出しますね、ちょっと待っててください」
「……いえ、結構ですよ。 大したことありませんので」
ジェイドはそう言うと、朝食もそこそこに椅子を引いて立ち上がる。
それは緩やかな拒絶だった。
そっとしておいてほしい、という合図のように感じられて、仕方なく棚から手を引く。
「そうですか? もし痛みや痒みが酷くなったら、病院に行ってくださいね」
「はい、そうします」
あまり信用ならないが、無理強いはしたくない。大人しく食い下がることにした。
彼は貼り付けた笑みのまま、名前を呼ばれて振り返る。
「なんでしょう?」
「今日は……先方との商談で遅くなるので、夕飯はいりません」
穏やかな口調、優しい声色、何もかもがいつも通り。それなのに突っ撥ねられたような印象を受ける。途端、彼の気遣いに対して、失礼だと自分を律した。
ジェイドが夕食を断るなんて、滅多にないこと。だからこそ、そういった印象を受けたのだろう。きっと余程大事な商談なのだ。そう思い直すと、ストンと腑に落ちる。先ほど感じていた違和感など、どこかに消えてしまった。
「わかりました、上手くいくといいですね」と、微笑んで快く送り出す。
途端、ジェイドの表情があからさまに強張った。何か殺気立ったものすら感じる。彼が私に向ける眼差しは優しいのに、酷く冷たい。穏やかな表情を浮かべているのに、どこか苛立ちを感じさせる。
そのちぐはぐさが、異質だった。
いつもの彼なのに、彼のはずなのに、ジェイド・リーチの皮を被った何かに思える。
それに気づかないふりをして、私は微笑んだ。
今できることは、それくらしか思いつかなかったから。
「……では、行ってきます」
「はい、お気をつけて」
彼はネクタイを首に掛けて、ジャケットと上着を素早く羽織ると玄関に向かう。
ほどなくして、扉が開き、そして閉じられた。
私はニュース番組をしばらく見て、今日の天気を確認するとテレビの電源を消す。
「……勿体ないなぁ」
彼にしては珍しく、その日の朝食はほとんど手付かずだった。
仕方なく流しに持っていくと、そのまま片付けてしまう。
今週は晴れの日がしばらく続くらしい。
それなら洗濯物や買い物に行くのに困らないな、と私は独り言ちた。
その晩、ジェイドは今朝言った通り、深夜を回っても帰ってこなかった。
商談、上手くいっただろうか。
そんなことを思いながら、就寝前にハーブティーを啜る。
寝る前はもっぱら読書が日課になっていた。ページを捲りながら、いいところに差し掛かった小説を読み進めていく。あと少し、もう少し……とページを捲る手が止まらず、ダラダラと時間が過ぎていった。
「こんなに面白いこの本が悪い」と誰に言うでもなく、言い訳を重ねる。
───チリン。
鈴を転がすような爽やかな音が鳴る。
この時間に似つかわしくない音に、どきりと肩が跳ねた。
夢中になって読み耽っていたので理解が遅れたが、玄関のチャイム音だと気づく。
「……こんな夜更けに? 誰だろう?」
恐る恐る、といった様子で自身の寝室から出ると、そぉっと足音を忍ばせて一階へ降りる。
チリン。
もう一度、呼び鈴が鳴った。
相手がまだ外にいることに、少し緊張しつつ声をかけてみる。
「あの、どちら様でしょうか?」
「こんばんは、元監督生さん」
聞き慣れた声が、すぐに返事を返す。
こんな呼び方をするのは、あの人くらいだ。
名前を出されずとも、すぐに誰かわかった私は鍵に手をかける。
「アズール先輩? 今開けますね」
かちゃり、と音を立てて玄関の扉が開くと、やはりそこには予想通りの人物が立っていた。元オクタヴィネル寮の寮長、アズール・アーシェングロットだ。
「相変わらず警戒心のない……改めましてこんばんは、ユウさん」
「こんばんは……」
呆れた様子のアズールに苦笑する。
それにしても何の用事だろう、と私の顔に書いてあるのを読み取ったのだろう。アズールは、すぐに肩を竦ませてため息をつく。
「夜分遅くに申し訳ありませんが、大きな荷物のお届け物です」
「小エビちゃん、久しぶり~」
途端、後ろからジェイドの兄弟である、フロイド・リーチが顔を出す。
「え、フロイド先輩までどうし……あ」
疑問を口にするまでもなく、その謎は解消された。
アズールの背後、フロイドが肩を支える人物は紛れもなく、ジェイドだったからだ。
なんとなく事情を読み取れたことが、表情に出ていたのだろう。アズールは「説明が要りますか?」と訊ねてくる。それでも一応お願いすると、眼鏡のブリッジを指先で押し上げて簡潔に話し出す。
「ジェイドが先方との商談後、かなり飲まされまして……幸い人前では平然を装っていたので面目は保たれましたが、会社に帰ってきた途端、酔いが回ったのかこの有様です」
「ん~……どこです……ここは?」
「うわ、マジでわかってなくてウケる~ ジェイドん家だよ」
「……と、このように泥酔していますのでロクに一人で歩けませんし、記憶も混乱しています」
「うわぁ……大変でしたね……皆さんお疲れ様です」
やれやれだ、と仕草が物語っていた。
それでもここまで送ってきてくれたのだから、面倒見が良いのだろう。何気に彼らは身内に優しい。
しかしだからと言って、決してそのことを口にはしない。もしちょっとでもそんなこと、口走ろうものなら、嫌そうに顔を顰めるのが目に見えている。
世の中には触れない方がいいこともある。そういうことだ。
「小エビちゃんじゃ重くて運べないと思うし、オレ今気分がいいから運んであげる~」
返事を返すまでもなくフロイドはズカズカと部屋に入っていく。そのまま勝手知ったるとばかりに、ジェイド寝室へ続く階段を上っていった。鼻歌まで歌っているのを見るに、かなり機嫌がいいのだろう。
気分屋で有名だった彼は、今でもその性分は変わらないようだった。
ありがたく、その厚意に甘えることにする。
「ありがとうございます、助かります」
「全く……どうせ明日は二日酔いでしょうから、最悪会社は休んでも構いません」
眼鏡のふちを指で押し上げると、アズールは嫌々といった様子で口を開く。
「体調が回復次第、いつも以上の働きを期待しているとでもお伝えくだされば結構です」
にっこりと笑うアズールは、果たして天使か悪魔か……それは神のみぞ知るところだ。
「はい、伝えておきますね……お茶でも飲んでいかれますか?」
「いえ、お構いなく。 またの機会にお邪魔しましょう」
「アハ、またねぇ小エビちゃん」
「はい、お気を付けて」
いつの間にか戻ってきたフロイドとともに、アズールは外に待たせた車に乗り込む。いかにもな、黒塗りの高級車だった。
玄関から見送ると、運転手が軽く会釈して走り去っていく。
私は玄関をそっと閉めると、鍵をかけて彼の寝室に向かった。
お盆にコップと飲み水の入ったピッチャー、そして二日酔いの薬をのせて運ぶ。
寝室の扉を三度ノックするが、中から返事はない。
「ジェイドさん、入りますよ」
仕方なく、渋々勝手に入らせてもらう。
「あの、お水は飲めますか?」
「ん~……」
彼は寝苦しそうに、ベッドの上で唸っていた。
これでは水を飲むことは難しそうだ。
「お水、ベッドの横に置いてますからね」
「ネクタイ、外しますよ……あと、第二ボタンまで外しておきますね」
サイドテーブルにお盆ごと置くと、彼のジャケットをなんとか脱がす。完全に脱力した成人男性の衣服を脱がすのは、なかなかに骨が折れた。かなりの重労働に、今日一番の疲労を感じる。
鬱陶しそうにしていた首元のネクタイを取り、ボタンを二つ緩めた。
すると少し楽になったのか、すやすやと眠りだす。悪化していないか気になって首元の虫刺されを確認すると、思っていた以上に斑点が広範囲にあった。少しびっくりする。
「……んぅ……ぁ……リカ……」
「え? なんて言いました?」
彼が何かを呟いた。耳を彼の口元に寄せる。ふわりと強いアルコールの香りがして、相当飲んできたことが窺えた。
「アン……ジェリカ……」
今度は先ほどよりも、はっきりと口にする。
それは女性の名前だった。多分、きっとそう。
掠れた声で囁かれたそれは、紛れもなく彼の浮気相手だろう。思わず、口角が緩む。そこには怒りや焦りなんてものは微塵もなくて、なんて微笑ましい牽制だろうと思えた。
きっとアンジェリカという女性は、ジェイドのことを本気で好きなのだろう。その証拠に、こんなに沢山の痕跡を残していた。朝になれば帰ってしまうジェイドに、少しでも爪痕を残したくて必死なのだ、きっと。
そっと居間からブランケットを取ってくると、彼に掛けてやる。
部屋から静かに出ると、私は何とも言い知れぬ高揚感に微笑んでいた。
これからの二人の出方次第で、随分と楽しめそうだ。
まるで自分がヴィランになったような気分でユウはうっそりと呟いた。
「まぁまぁ、可愛らしいことですね」
●
「おは、よう……ございます」
「あ、ジェイドさん、おはようございます」
掠れた声が背後から聞こえて、振り返るとジェイドが立っていた。
壁に掛けられた時計を見るなり、顔を顰めている。普段なら出社している時間だ。
いつも通りならすでに身支度を整えて、バリバリと仕事をこなしているだろう。
時計の針は午前十一時を指示していた。
ユウといえば朝食を終えて、洗い物を片付けている最中だったが、蛇口を捻ると水を止めてタオルで手を拭く。そしてポットからコップに白湯を注ぐと、ジェイドに差し出した。彼は素直に受け取ると、ぬるめの白湯に口をつける。
「ご気分はどうですか? 頭は痛みます?」
「昨日、僕は……どうやって……?」
「アズール先輩とフロイド先輩が送ってくださったんです」
「ああ、そうでしたか……」
納得がいったのか、彼は頷いた。
昨夜の記憶がない上に、朝起きてみれば自宅にいるのだから驚くのも無理はない。
いかに商談の取引相手とはいえ、意識がなくなるまで飲ませるなんて、やりすぎだろう。アルコールハラスメントではないだろうか。彼の健康が心配だった。
「アズール先輩が今日は体調が悪ければ、会社を休んでも構わないと仰ってましたよ」
「……そうですか」
「まだ、辛そうですね」
「……これくらい、どうということは……」
「ダメですよ、ちゃんと休息も取らないと」
「……」
ジェイドは珍しく、黙ってしまった。
これは相当、身体に堪えているのかもしれない。
何の表情も浮かべないまま取り繕うこともせず、ただ視線はコップの中に注がれている。
そのまま大きく息を吐いて、何かを考えるように眉間に手を当てた。
「アズール先輩には、私からお休みの連絡入れておきますね」
彼に緩く微笑んで、スマートフォンをエプロンのポケットから取り出す。
アズール先輩の名前を電話帳から見つけると、タップしようとした。
が、その手首を掴まれる。
なんだろう、と見上げた先には、表情を削ぎ落した真顔の彼がいた。
「……勝手なことを、しないでいただけますか」
「え?」
苛立ちを含んだ低い声色に、思わず困惑の言葉を溢す。
身体が不自然に固まり、浮かべた微笑みが消えていく。一気に全身の体温が下がり、凍り付くかのように居心地が悪い。私の反応一つ一つ、それすら不愉快だとばかりに彼は手首を掴む力を強める。
「あなたの気遣いは無用のものです、言わないとわかりませんか?」
「……ごめんなさい、でも……」
「僕は体調が悪いなんて一言も言っていませんし、ましてや会社を休むとも言っていません」
彼はそこまで言うと、掴んでいた手首を雑に離した。普段のように、壊れ物を扱うような丁寧さや優しさは欠片もない。
いきなり態度が急変して、あまりにも突然のことに理解が追い付かない。
離された手首は少し赤くなっていて、スマートフォンを胸の前で守るように両手で握りしめる。
「大体、最近あなたは勝手が過ぎる」
「ぇ……あ……」
「誰のおかげで生活して暮らせているか、よく考えてみては?」
「……すみません、生活費、使いすぎてましたか?」
突き刺すような、嫌みな言葉。それらが彼の口から放たれる度、まるで悪い白昼夢を見ているかのような心地になった。心臓が嫌な音を立てて、皮膚が粟立つ。普段のジェイドからは想像できない、棘を含んだ物言いだった。
「……はぁ、そうではなくて……もういいです、話になりません」
彼のことをこれ以上刺激しないように、謝罪する。しかし、取り合ってもらえない。
背を向け、その場を後にしようとするジェイドの手首を、縋るように掴む。
ほんの僅かに彼の動きが鈍くなって、ぴたりと止まった。
せめて、せめて話してほしかった。理由があるなら、何が嫌だったのか、何が不満だったのか。改善できることなら、努力だってしようと思った。彼がこんなに怒るまで気づけなかったことが、申し訳なくて居た堪れなかった。
「あの、ジェイドさん……次から気を付けるので……何か気に障るようなことをしてしまったなら、教えてくれませんか?」
「……っ鬱陶しいんですよ、そういうところが!」
彼の怒声にびくりと肩が震える。
途端、弾かれたように彼が手を払い除けて、私の身体はバランスを崩して左後ろに倒れた。彼の手にしていたコップの白湯が、服と顔面にかかる。目を瞑ったせいでろくに受け身をとれなかった。壁に頭を強打してしまい、苦悶の声が漏れ出る。手にしていたスマートフォンも衝撃で遠くに飛ばされてしまった。
「っっ……い、た……」
「あ……」
痺れる手足に力が入らず、ズキズキと痛む頭を弱々しく抱えると、慌ててジェイドが駆け寄ってくる。その様は先ほどの様子とはかけ離れた、いつもと同じ優しいものだった。頭を抱え、痛みに耐える私にひどく狼狽えている。
「ぁ……あの、ユウさん……すみません、力加減を間違えました」
「お怪我は、ないですか?」
「痛みますよね……すみません、僕、頭が痛くて変なことを言って……立てますか?」
彼の表情には、不安と動揺がありありと見て取れた。
自分でも予想外の出来事だったのか、あからさまにしおらしくなる姿からは反省の色が窺える。跪き、おずおずと差し出された手をしばらく見つめて、私は微笑んだ。
安堵の表情を浮かべるジェイドにユウは何も言わず、瞼を伏せる。
きっと彼は、この微笑みの意味を知らない。
「……三回目」
ぼそり、と呟かれた言葉にジェイドは耳覚えがない。
今度は彼が困惑する番だった。
「……え?」
ユウは彼の手を取ることなく、自力で静かに立ち上がる。
そのまま遠くに飛ばされたスマートフォンを拾うと、居間から自室に繋がる階段を上っていった。
彼女の動向をしばらく呆気にとられて見ていたが、すぐに後を追いかける。
心がざわついて、酷く嫌な予感がした。
「あの、ユウさん……?」
ノックをして入るまでもなく、半開きになった扉から中を恐る恐る窺う。
ユウからの返答はなく、ただただ静かだった。彼女は怒りも拒みもしないが、その代わりに無言を貫き通す。一度決めると、何があっても一貫した姿勢を示す姿は、学生時代から変わらない。
彼女は何か用意をしていた。初めてこの家に足を踏み入れた時に持参した、くたびれた革のカバンに何かを詰め込んでいる。見るからに必要最低限の衣服、スマートフォン、ノートパソコンを丁寧にしまうと自身の身に着けていたエプロンを取り、綺麗に畳んで机の上に置く。
彼女のすることを暫く黙って見守っていたが、クローゼットに手をかけたことで心臓が嫌に早鐘を打つ。
何着か取り出しては見て、取り出しては見てを繰り返し、そのうち一着に決めたのかハンガーから取った。
それはユウが働いて自身で貯めたお金で買った、真っ黒のロングコート。
それをいそいそと羽織り始めたので、慌てて断りもなく部屋に入る。
「……ど、どこに行くんですか?」
「……」
彼女は何も言わなかった。
ただ黙って微笑んだ。
彼女の声が聴きたい、何か言ってほしい。それが例えジェイドを罵る言葉だろうが、何でも良かった。
今は沈黙が、何よりも怖い。
「せめて、説明を……」
余裕のないジェイドは彼女の肩を両の手で掴んだ。
できるだけ、可能な限り優しく、怖くないように。
それを一瞥して、ユウはジェイドの顔を見上げた。
じっと両の瞳で見つめられて、微笑みを浮かべているのに何の感情も色も映さないそれに、背筋が凍る。あどけなさの残る可愛らしい少女の顔は鳴りを潜め、大人びた眼差しがジェイドに向けられていた。彼女から目が離せない。
暫くしてようやく、ユウは口を開いた。
さっきまであんなにも彼女の言葉と声を求めていたのに、今は最後の判決を聞く罪人の気分だった。聞きたくない、と矛盾した気持ちが湧き起こる。
「私の故郷の言葉、ことわざに〝仏の顔も三度撫でれば腹立てる〟というものがあります」
静かな語り口だった。
どこまでいっても穏やかで、何もかもを許しているような声色と表情に、見入ってしまう。
「どんなに温和な人であっても、無法なことをたびたびされると、しまいには怒ってしまうというたとえですね」
彼女はそっと肩に乗ったジェイドの手に、自身の小さな手を重ねた。そして片方ずつ丁寧に引き剝がす。それはユウから送られる初めての、緩やかな拒絶だった。彼女の肩に触れていた手が、引き剥がされた指先が小さく震えている。
悲しかった。つらかった。痛かった。
様々な感情が綯交ぜになって、ジェイドの思考を圧迫する。
今までユウから与えられた優しさの温度の分だけ、ズキズキと胸が痛んで冷たくなっていく。彼女の拒絶は優しくて、温かくて、罪人には残酷だった。
「私、実は密かにカウントしていたんです」
ユウは楽しげに口にする。
まるで簡単な仕掛けが成功した幼子のような、微笑みを浮かべて。
それだけで、彼女が何を言いたいのか分かってしまう。耳を塞ぎたい衝動に駆られた。
「それが、今日で三回目だったので……もういいかなって」
涼しげな顔でさらりと言ってのける。
心臓が痛いくらいにどくどくと早鐘を打ち、彼女の言葉を待っている。
けれど、先に続く言葉に未来などなくて────
「私は私を大切にしてくれる人が好きです」
「まって……待って下さい、どういう……」
「ご自分が一番理解しているのでは?」
「……っ」
彼女は穏やかな表情を浮かべていた。
まるで絵画の中の聖母のように、すべてを許していた。
怒りや嫉妬や悲しみに塗れ、汚れた僕とは比べるくもないほどに、綺麗だった。
話は終わりだとばかりに去ろうとする彼女の行く手を全身で阻む。
「どいてくださいますか?」
「あなたはこの家から出て行っても、行く当てがないでしょう」
それは脅迫に近かった。
唯一彼女を留めておける足枷だった。だから、卑怯にもその言葉を選んだ。
それが悪手だとも、その時は気付かなかった。そんな余裕はジェイドになかった。
「はぁ……ご心配には及びませんよ」
呆れた様子で彼女はまた微笑む。
「私、別にジェイドさんがいなくても生きていけるんです、実は」
言葉が刃のように、身を貫いていく。あまりの衝撃に、自分の自惚れと愚かさを知った。
焼印を押されたように、患部がじくじくと痛む。カッと全身を巡る血液が熱くなって沸騰しそうだった。
縋るように彼女の服の袖を掴む。動揺から焦点が定まらない。
「そんなの……嘘だ……うそ、でしょう?」
「ふふ、本当ですよ」
揺れる視界の向こうで、彼女は嬉しそうに笑う。
まるで鳥籠から飛び立つ瞬間の、囚われの小鳥のようだった。
ジェイドの両足から力が抜けて、膝をついた。
彼女の服の裾を掴む指先から、力が緩む。
「そ、んな……」
「さようなら、今までお世話になりました」
「ジェイド先輩」
それを見計らったように、ユウは腕を引くとカバンを手に取る。
いともたやすくジェイドの手は退けられて、項垂れる彼の横をユウはするりと抜けていく。
しばらくしてガチャリ、とドアの開く音がした。
先ほどまで感じていた彼女の温もりは、もう、ない。
ただただ、静か。
「……ユ、ウ……」
呟いた言葉は、彼女の名は、むなしく空に溶け消える。
孤独感と尽きぬ後悔が、身を蝕んでいった。
もう、何もかも後の祭りだった。
●
始まりは、明確に自覚している。
彼女が洗濯物をしていたから手伝おうと思って、下の階に降りた時だった。
声をかけようとして、けれどかけられなかった。ひやりと背を冷たい汗が伝う。
彼女は昨日、ジェイドが着ていたワイシャツの襟元を指先で撫でていた。その箇所には、赤いシミが付着している。それは浮気の証拠に為り得ても、仕方ないものだった。
昨夜の商談相手は、女性関係にだらしのないことで有名な人間だ。先方の指定で向かった場所は、商談の場にふさわしいとは言えないような店だった。若い着飾った女性を両脇に侍らして、酒を煽りながら酔いの回った赤ら顔でペチャクチャと話す。実に小汚い金だけが取り柄の男だった。
ジェイドの両脇にも女性を座らせて、すり寄ってくる彼女らを適当にあしらいながら商談を進めた。
内心、ユウ以外の女性に触れられるなんて、気持ちが悪く不愉快だった。が、これから取引先になる先方相手に事を荒立てることはない。できるだけ速やかに、けれどそれを悟られないように、進めていく。
その日、帰宅したのはかなり遅い時間でユウは眠っていた。疲れと酒のせいもあり、ワイシャツや服の匂いにまで気を遣えなかった。きっと彼女が手にしたワイシャツは、きつい香水の香りがしていることだろう。
気が気でないジェイドは、なんとか誤解を解きたかった。
ユウが離れていく未来を想像して怯えることしかできない。
怒るだろうか。
悲しむだろうか。
それとも、嫌いになるだろうか。
未だ、小首を傾げつつジェイドのワイシャツを手に持つ彼女。
それに不安は大きくなるばかり。けれど予想に反して、ユウは機嫌よくワイシャツの染み抜きを始めた。鼻歌まで歌って、微笑みながら。
その時からだ。自分が変になったのは。
何か、胸に痞えたような心地がした。
大切に、心から愛していた彼女のことを、憎いとすら感じるほどに。
どうすれば彼女から、その微笑みを奪えるのか。
余裕を消せるのか。自分のことで満たせるのか。
そんな不純な感情が芽生えた。
そこからは自分との戦いで、度々襲い来る衝動を理性で無理やり押さえつけた。
彼女のことを傷つけたい。いいや、傷つけたくない。
ユウを悲しませたい。いいや、悲しませたくない。
相反する感情が、否が応でも押し寄せてくる。抑え込めなかった分だけ、彼女との約束を反故にした。そして、いつのまにか深みに嵌って抜け出せなくなった。
わざと見せつけるように誘導したキスマークを、虫刺されだと言われたときは安堵した。だが、酷く気分が悪かった。どうすれば、彼女は揺らぐのか。その在り方を、歪ませられるのか。わからなかった。
僕だけが苦しんで藻掻いている現状が、どうにも腹立たしく不愉快だった。
きっと心のどこかでは、嫉妬や悲しんでくれる姿を期待していたのだろう。
馬鹿馬鹿しい、幼稚な感情に振り回されて、結局最後にはすべて失った。
彼女が家を後にしたその後の記憶は、よく覚えていない。
しばらく膝をついたまま、項垂れていたように思う。
ふと、窓の外を見ると日が暮れかかっていた。もうじき夜が来る。
────夜が。
瞬間、ぶわっと焦りが募る。今、ユウは寒空の下、一人きりだ。夜道を非力な彼女一人で歩かせるなんて、そんなことできない。きっと強がっていただけで、まともに所持金だってないはずだ。泊まる所も、寝る場所もないはずだ。そんな可哀想なことを強いてしまった己が、憎くて憎くて堪らない。思考が自己嫌悪から抜け出せない。
けれど、それでも。
「探さないと」
うわごとの様に呟く。
「彼女に、謝らないと」
きっとまだ間に合う。
そう信じるしかない。
よろよろと立ち上がる。
足早に自分のスマートフォンを引っ掴むと、電話帳を開き彼女の名前をタップする。
無論、返事はなく留守番電話となった。
次にマジカメのアカウントを開いて、フォロー欄から彼女の名を探す。アカウント自体はあるのに、ブロックされてメッセージも送れない。メールもダメだった。
次に片っ端から知人に電話をかける。学生時代の友人や先輩後輩、王族貴族関係なくかけた。求めていた情報も答えも、得られなかった。冷静に努めているつもりだったが、声色に滲み出ていたのだろう。電話口の相手は口々に訝しんでいた。
なんでもない、と取り繕うのは無理があった。けれど、なけなしのプライドが邪魔をして無難な言葉を口にする。それに相手は渋々といったような形で返事を返した。
特に彼女と親しかった友人、エース・トラッポラ、デュース・スペード、グリムの三人は挨拶もそこそこに、開口一番「何かしたんですか?」と棘を含んだ声色で訊ねた。そして取り繕うジェイドに「もし何か知ったとしても、教える義理はない」と突っぱねた。
当たり前だが、彼らは何があっても彼女の味方だろう。
居ても立っても居られなくなって、近辺をくまなく探した。駅員やバスの運転手にも聞き込みをした。電車にも乗って、隣町やその次の街にも降りてみた。彼女の姿を求めて、付近の街を終電まで歩き回った。
けれど、彼女の痕跡は一欠けらだって得られなかった。情報も何もかも。
日付がとうに過ぎて、手足は冷たくなり、歩き疲れた足は痛んだ。それでも彼女の身が心配で玄関の外でじっと待っていた。彼女が凍えながら帰ってくるかもしれない、そう思って部屋を暖めて待っていた。けれど、いくら待てど、ユウは帰ってこなかった。
「……ん」
いつの間にか寝てしまったらしい。膝を抱えて、蹲っていた。
手はかじかんで、ロクに力が入らない。身体がガクガクと寒さに震えた。
人間の身体は脆い。そしてすぐに壊れやすい。
人魚であり、変身薬を飲でいるジェイドは普通の人間よりもいくらか丈夫だ。力も強いし、寒さにも強い。けれど人間になっている今、それには限度があり、幾らか本来の姿より弱体化している。
────元々人間の彼女に、きっと、この寒さは耐えられない。
疲労の限界を感じながら、一度家の中に入る。
回っていない頭で必死に次の算段を組もうとするが、今のジェイドには難しい。重たい足が勝手に寝室に向かい、自分の意思とは関係なく扉を開ける。
寝室には昨夜着ていたジャケットとネクタイが、丁寧にハンガーに掛けられていた。
「ユウが……してくれたのでしょうね」
勿論、返事はない。
ベッドに身を投げると、もう動けなかった。一歩たりとも、ここから動けない。そう思った。
ふとサイドテーブルを見る。
二日酔いの薬、ピッチャーに入った水、コップが置いてあった。
彼女が置いてくれたのだろう。メモまで残してある。
〝一日三回、一回二錠、食前に飲んでくださいね〟
少しクセのある字体はまさに彼女のものだ。可愛らしいにっこりマークまで書いてある。
「う……ぅ゛う……どうして……僕は……」
────僕は、なんて浅はかなんだろう。
こんなにも自分を想ってくれた大切な存在を、傷つけ、試して、それでいてまだ求めている。彼女の身を心配しながら、その実自分が可愛くて仕方ないのではないか。己にとって都合のいいことばかり、妄想しているだけではないか。
今まで自分のことを、こんなにも責めたことはない。
嗚咽とともに、とめどなくこぼれ落ちる涙さえ、苛立ちを加速させる。
帰ってきてほしい。口を利かなくていい。僕の存在を無視してもいい。金目当てでも、なんでもいい。なんでもいいから。
お願いだから、どうか……帰ってきて。無事でいてください。
────あなたの身が心配で胸が張り裂けそうだ。
後悔が、自身への失望が、ジェイドの身を蝕んでいく。
悪い夢なら覚めてほしかった。
ポケットのスマートフォンがけたたましく鳴っている。
何度も何度も何度も。いい加減あきらめてほしい。
うるさいと思って、けれどすぐに飛び起きた。慌ててスマートフォンの画面を見る。しかしそこに望んだ名前は、表示されていなかった。着信履歴は、全てアズールとフロイドで埋まっている。メッセージも何十件か残っていた。
大方、仕事のことだろう。昨日から無断欠勤を重ねてしまっている。
だが、今はそんなことどうでもよかった。些細なことだ。
いつもなら微笑ましく聞けるアズールの小言も、聞きたくない。鳴り続けるスマートフォンを無視して、一階に続く階段を下りる。
喉の渇きを覚えて、冷蔵庫の扉に手をかけた。中には彼女が用意してくれた常備菜と、昨晩のおかずがタッパーで置いてある。
台所のシンクを見ると清潔に保たれていて、ピカピカとしていた。居間は綺麗に整えられているし、テーブルの上にはジェイドが好きだと言った果物、パン、お菓子が籠に盛って置いてある。
隅々まで彼女の優しさで保たれていた空間は、言うなればジェイドのための楽園だった。
勘違いをしていた。彼女のために作り上げたと思っていたこの家は、いつの間にかユウの手によって、ジェイドが一番心地よく過ごし暮らせる場所へと変貌していたのだ。
彼女の細やかな気遣いが日常と化していて、気づけなかった。
「あなたの優しさに、胡坐をかいた罰ですね」
ほろり、と片方の目尻から水滴が落ちる。
それが涙だと、頭では理解していた。
けれど、自分が泣いている実感が持てなかった。
「あ、……ぁあ……」
両の手を見る。
何の汚れもないはずなのに、ジェイドの目には真っ黒に薄汚れて見えた。
ぽたり、ぽたり、と水滴が落ちて手のひらを湿らせる。
「どうしたら、いいんでしょうか……どうしたら……帰ってきてくれますか?」
震える両の手で顔を覆って、情けなく泣いた。嗚咽が止まらない。
掠れた声で彼女の名前を祈りの言葉みたいに呟いた。
今のジェイドにはそれしかできなかった。
●
彼の家を出てから、一か月ほど経った。
あの日から一週間は怒涛の日々だった。
ホテル生活を送りながら、不動産会社を訪れて部屋の下見や契約なんかを済ませた。その後案外早くに住居に移れたので、助かったのは言うまでもない。
インテリアの類はおいおい揃えるにして、ベッドだけは必要だろうと前から目をつけていた家具の店で、マットレスとともに購入した。
まだベッドしかない部屋ではあるが、自分の城ができたみたいで胸が躍った。
彼と過ごした家の広さとは比べようもないが、一人暮らしに全く問題ない広さだ。元いた世界の家よりも天井が高く、開放感のある室内に満足している。
七階建てマンションの五階に位置する私の部屋は日当たりもいいし、何より角部屋だ。住人も親切で、気立てのいい人が多い。
改めて、ジェイドに甘えず仕事をこなし、貯金していて良かったと思う。
彼との連絡関連は全て絶ち、マジカメアカウントやメッセージアプリも全てブロック。
自宅でパソコン一つあれば行える仕事や内職をこなし、好きな時間に外に出て帰ってくる。
充実した日々を過ごしていた。
「……さてと、買い物でも行こうかな」
仕事がひと段落したところで、頭の上で手を組んで伸びをする。
ジェイドから生活費をもらっていた頃とは打って変わり、抑えるところは抑えての節約生活だが、これはこれで楽しい。ナイトレイブンカレッジ在籍中の学生時代のことを思えば、なんてことはなかった。
ふいにスマートフォンが鳴って画面を見れば、相手は非通知。
「誰だろう……」
思わずぽつりと呟く。
仕事の関係だったら困ると思い、恐る恐る通話ボタンを押す。
「もしもし」
「あ、繋がった! ……小エビちゃん、元気そうじゃん」
久々の聞き慣れた声に、独特の愛称、名前を言われずとも誰かわかる。
「フロイド先輩?」
「そ、フロイドでぇ~す」
声色から、今は機嫌がいいのだろうと窺える。
今まで連絡も何もなかったのに、急にどうしたのだろう。
大方、片割れのジェイドのことだろうが、私には応じる義理もない。
むしろ、被害を被ったのはこちらである。いつもなら彼の付けた愛称よろしく、小エビのようにびくびくと震えるところだが、今日に限ってそれはない。
「急にどうしたんです? 何か御用ですか?」
「うん、その……」
フロイドは珍しく言い淀む。
これは確実に十中八九、ジェイドのことだろう。
「あの、申し訳ないのですが、ジェイド先輩のことならお断りし「ま、まって! そうなんだけど違うから! いや違わないけど……」
用件を聞くまでもないだろう。
そう思ったが、言葉を発する前に被せられる。
随分切羽詰まった様子に、少し興味を惹かれて話だけは聞くことにした。
「……ご用件は?」
「おねがい、オレに免じてぇ……一回だけジェイドに会ってやってくんない?」
「フロイド先輩がそんなにご兄弟想いだったとは、知りませんでした」
少々冷たい物言いになってしまったが、仕方ないことだと割り切る。
時間は有限だ。今この瞬間を、彼の問題で奪われるのは気に食わない。
フロイドはあからさまに落ち込んだ声色で「それは……ちげぇけど……」と、納得いかない様子で答えた。その後で「あ、そうじゃなくて!」と脱線しかけた会話を軌道修正する。
「……ジェイドが悪いのは知ってる……殴ってもいいからさぁ、ね?」
「はぁ、要件がそれだけなら、失礼しますね」
耳元からスマートフォンを離し、通話の終了ボタンに指をかけた。
すぐに大声で「ま、まって! 小エビちゃん!」と焦った声が飛んでくる。
こういうのは無視だ、無視。彼相手に後が怖いが、兄弟のしでかしたことを知っているのなら、大きくは出られないだろう。
「ジェイド、自殺しかけて…………あ」
「え?」
指先がボタンに触れる直前だった。
耳を疑う単語に、途端手が止まる。
自殺? 誰が? ジェイドが? あのジェイド・リーチが?
なんのために? まさかとは思うが私のせいで?
困惑の面持ちで耳元にスマートフォンを再度当てる。
「それ、本当なんですか?」
「しくった、口止めされてたのに言っちゃったぁ……」
フロイドの様子や言葉から、どうやら未遂に終わったことはわかる。
しばらくの間、沈黙が落ちた。二人とも何も言わなかった。
強いて言えばフロイドは、言えなかったの方が正解に近い。彼女がただの小エビではないことを知っていたからこそ、相手の出方を窺っていた。
ユウといえば、頭の中で情報を整理していた。湧き上がるいくつもの感情を抑え込んで、なんとか言葉を絞り出す。
「……どこに行けばいいんですか?」
電話越しに聞くユウの声は、温度を感じさせない。
学生時代、オクタヴィネル寮でひと悶着あった以来向けられる冷たい声色に、フロイドは表情が強張っていく。
「来てくれるの……?」
「少し、用事ができたので」
淡々とした口調だった。
ユウの気が変わらないうちに、なんとか事を運ばなければいけない。
「それで、どこに向かえばいいんです?」
「……ジェイドん家」
「わかりました、今から伺います……ただし一つ条件が」
「なぁに?」
「フロイド先輩もしくはアズール先輩、どなたでもいいですけど……第三者同伴でお願いしますね」
まるでアズールのような物言いに、フロイドはどんな無理難題が来るのかと身構える。しかし提示された条件は単純で容易くて、頷く以外に選択肢なんてなかった。
落ち合う時間と場所を決めると、通話を切る。
新しく新調したコートを羽織り、マフラーを首に巻く。
どんよりとした薄暗い雲が垂れ込め、今にも雪が降りそうな空模様だ。こんな日は家でゆっくりするに限るのだが……そうもいかなくなった。
ハンカチ、口紅、スマートフォンの最低限を上着のポケットに突っ込み、外に出ると玄関の鍵を閉める。
木枯らしの吹く住宅街を足早に抜け、駅に向かう。葉が落ちて裸になった街路樹が、余計に寒々しさを助長させた。
途中、道に面した製菓店のショーウィンドウが目についた。
こじんまりとした店内で、色とりどりのケーキや焼き菓子が、宝石みたいにきらきらと輝いていた。
彼との始まりも、手土産のケーキからだったことを思い出す。
それなら、終わりもケーキが相応しいだろう。
────これが終わったら、ケーキを買いに行こう。
一人頷いて、ユウは雑踏の中に紛れていった。
●
「すみません、お待たせしました」
目的の駅に着くと、改札を抜けた先に彼らは待っていた。
後ろには黒塗りの高級車が控えており、汚れ一つない。
上質なスーツを着込んだ容姿端麗な二人に、いかにもな車。この場所で浮くには、十分な条件が揃っていた。通行人はちらりと視線をくべて、各々目的の場所へと向かっていく。
「……いえ、僕たちも今来たところです」
「そうそう、全然待ってないし」
私の予想に反して、フロイドのみならずアズールまでもが同行してくれるようだ。こんな状況ゆえに、彼らの表情は硬い。
対して私といえば、穏やかな笑みを浮かべていた。
ぎこちない二人に、立場が逆転したような心地だ。
「お二人ともお忙しい中、ご足労いただきありがとうございます」
「それは……あなたも同じでしょう」
「私たち、みんな彼の被害者ですね」
アズールが目を伏せ、言いづらそうに呟く。
それに苦笑しつつ、冗談を返したつもりだった。
が、反応しにくかったのか、二人とも押し黙ってしまう。
あんまり面白くなかったかな……と、己のジョークセンスのなさに少し落ち込む。
「……では、行きましょうか」
アズール自ら高級車のドアを開けて中に入るよう促す。それに礼を言って乗り込んだ。
運転手が車を出すと、景色が動き出す。流れていくネオンの光が、夕闇の中で綺麗だった。
車内には異様な空気が流れている。久々の再会だというのに、誰も会話を交わすことはない。私も無理に話すことはないかと思い直して、革張りの座席に背もたれ、窓の外を眺めた。
ジェイドの家に近づくにつれ、少しずつ懐かしい景色が広がっていく。
しばらくしてとうとう、見慣れた家の前に車は止まった。
「着きました、どうぞ」
「ありがとうございます」
運転手はすぐにドアを開けて、恭しく一礼する。
礼を述べて車から降りると、続いて二人も降り立った。
周辺の家々は明かりが灯っているのに、ジェイドの家だけは真っ暗だ。
本当にこの中に彼がいるのだろうか、と疑問すら浮かぶ。
「ユウさん、こちらです」
「ジェイドぉ~、入るよ~」
アズールが開錠し扉を開けると、フロイドが大きな声を出しながらズカズカと先に部屋に入っていく。まるで我が家のような自然体だった。それに続いて私も入ると、アズールは静かに扉を閉め電気を点ける。
真っ暗だった室内を、温かみのある色の明かりが照らし出す。見る限り室内は私が出ていった時と同じく、綺麗に保たれていた。特に散らかった様子もない。唯一違いといえば、玄関先に飾った花瓶の花が、萎びて枯れていることくらいだった。
二階から降りてきたフロイドが首を横に振る。どうやら自室にはいないらしい。
「ジェイド、入りますよ」
アズールが声をかけながら、居間に続く扉を開ける。
フロイドも続いて入ると、電気のスイッチを押した。ユウは彼らの背後から続いて中に足を踏み入れる。
自殺未遂だというから、どんな有様かと恐れていた。しかし、どうということはない。散らかった形跡はなく、清潔に保たれた室内はあの時のままだ。暖房をつけていないのか、中はかなりひんやりとしている。
辺りを見回すが彼の姿はない。フロイドとアズールも顔を見合わせて、眉を顰めている。
私は特に何もせず、事の成り行きを見守っていた。ふと思いついたように、フロイドがキッチンの方に足を向けた。そして、くるりとこちらに身を捻る。
「ジェイドいたぁ」
「はぁ、居るなら返事くらい、したらどうです?」
フロイドはニヤリと笑った。
アズールが呆れた様子で文句を言いながら、そちらに近づいていく。
彼らの背後からそっと様子を窺うと、冷蔵庫に背もたれて片膝を抱え蹲るジェイドがいた。いつもと同じ出社前の格好なのに、着ているシャツは着崩れて、だらしがない。ネクタイとジャケットは乱雑に床に散らばっている。
視線は虚ろで、こちらの声がしても反応を返さない。むしろ、鬱陶しいと言わんばかりに顔を背ける。ふと足元を見れば、お酒の缶や瓶が大量に放置されていた。
「全く、どこまで迷惑をかければ気が済むんですか?」
「オレもそろそろ疲れてきたし、いい加減にしてくんない?」
苛立ちを含んだ二人の声に、ジェイドは煩わしそうに目を瞑る。
「……る……ね」
「あ? なんて?」
ぼそぼそと呟かれた言葉は、何を言っているのか聞き取れない。
フロイドが身を近づけると、ようやく聞こえる大きさで気だるげに呟く。
「……うるさいですね、仕事はちゃんとこなしているんですから、ほっといてください」
「恋人に振られたくらいで……ここまで落ちぶれるなんて、嘆かわしい」
「……何がわかるんですか、アズールに」
「お前がしたことの、ツケが回ってきただけでしょう」
「そうそう、ジェイドがぜ~んぶ悪いよねぇ」
「……目障りです、消えてください」
二人の言葉に痺れを切らし、ジェイドが手元にあった空き瓶をこちらに投げつける。
身構える間もなく飛んできた空き瓶がユウの顔に触れる直前、アズールの手がそれを阻んだ。パシッと乾いた音がいて、しっかりと握られた瓶が目の前でぴたりと止まる。
「……ひっ……!」
「え……?」
思わず恐怖から漏れ出た声に、ジェイドはゆっくりと顔を上げる。
驚愕に見開かれた瞳と視線がかち合い、表情が一気に強張った。
「ジェイド」
アズールは低い声で、唸るように彼の名を呼ぶ。
「お前が会いたくてやまないお方をお連れしたのですが、どうやら無駄な気遣いだったようですね」
嫌悪感を声色に滲ませて、アズールは皮肉たっぷりに言った。
そしてユウの姿を隠すように、前に一歩出る。
「申し訳ありませんが、お帰りいただきま───「ユウさん……! お怪我は⁉」
途端、ジェイドは弾かれたようにアズールの身体を跳ね除けて、ユウの傍に駆け寄った。肩を掴む指先が、ガタガタとみっともなく震えて、目の下には濃い隈ができており、少し痩せた様子だった。以前よりもやつれた印象を受ける。
「痛みは⁉ 当たってないですか⁉ 怪我は……っ」
「アズール先輩のおかげで無傷です、ご心配なく」
「す、すみません、僕はてっきりアズールだと……ばかり……本当にすみません」
慌てて肩から手を離すと、項垂れて顔を覆う。
悲痛な面持ちで目を伏せるジェイドを覗き込む。
「ジェイドせ「わかってます! 僕がすべて悪いんです!」
堰を切ったように、自身の過ちを口にする。
その様子を、二人は黙って見ていた。
「全部、ぜんぶ、僕が悪い…………」
「何か、そんなに悪いことをしたんですか?」
あえて試すような訊き方をした。
それにあからさまに動揺した。彼は視線を落とす。
「そ、れは……あなたを、試すようなことを……したから………」
途切れ途切れに、言葉を口にする。
歯切れの悪いジェイドなど、普段なら見ることは叶わないのでレアな光景だ。
「……あなたの……嫉妬した姿を見たかった」
ぐしゃりと前髪を掴み、俯く。
ぽつりと溢した本音は、なんとも幼稚なものだった。
嫉妬という単語を噛み砕いてみる。
けれど舌の上でいつまでも溶け切らないそれは、飲み込むことができない。
理解できない、と思った。彼の思考が、考えが、求めていることが、頭では解っても、それを叶える術は分からない。
わからなかった。理解できるのに。
相容れない生態に触れて、自身との隔たりを肌で感じる。
「あなたに、愛されている実感が欲しかった……それだけでした」
「だから、その………嫌々他の女性と過ごしたり……わざと遅くに帰ったり……門限や決め事を破りました」
「それは僕の身勝手な想いで、浅はかな感情でした……勿論、何度もやめようとしたんです、本当に」
「何度も何度も……自分の衝動を抑えつけました……だけど、最後にはあなたに当たって、傷つけてしまった」
ジェイドは懺悔するように、苦しげに呟いた。
誰も何も言わなかった。ただ、彼の言い分を黙って聞いていた。
「僕のことを罵っても、殴ってもいいです……いえ、殴ってください……それくらいしないと、フェアじゃない」
「お願いします……これ以上、嫌わないで……」
弱りきった声で懇願されて、まるで私が悪いことをしたような気分になる。
畳み掛けるように、ジェイドはユウの手を握る。
優しく、壊れ物を扱うような、そんな触れ方だった。
「どうか、帰ってきてくださいませんか?」
うるんだ瞳に、しおらしい態度、反省の色は窺える。
それに小さくため息を吐いて、私は彼の名を呼ぶ。
「ジェイド先輩」
「……はい」
「私が今日、ここに来たのは、一言申し上げたいことがあったからです」
「はい……なんでもどうぞ」
「では、遠慮なく」
いつものように穏やかな微笑みを浮かべれば、ジェイドの強張った表情が喜びで緩む。
先ほどまでの張り詰めた空気から、打って変わり大団円を迎えるかのように温かな雰囲気が流れる。「やれやれ、丸く収まった」とばかりに目配せを交わすアズールとフロイドの様子が、ちらりと視界の端に映った。
はぁ、つくづく私も救いようがない。
だって許すも何も、怒ってすらいない。
「ジェイドさん」
至極優しい声色で、まるで愛を囁くように、彼の名を口に出す。
幸福と期待に満ちた眼差しが、ユウに向けられた。それに応えるように緩く微笑んで、私は彼の手をするりと解く。
そのまま右手を彼の襟元に添えると、勢いよく引っ掴み、ぐっと力強く引き寄せる。鼻先が触れあいそうな距離になったことで、ジェイドは目を見開いた。ユウは笑みを深める。
──────ああ、なんて馬鹿な人なんだろう。
「頭、お花畑なんですか?」
「───え?」
「「は……」」
まるで何もかも許したような表情で、ユウはジェイドに訊ねる。
先ほどまで流れていた温かな空気は、一瞬にして凍り付くような冷たさに変っていく。
異質だった。何もかもが。彼女の身を包む雰囲気も、笑みも、声も。まずもって、許す、許さない以前の問題だ。そもそも、彼女は許すとは言っていない。怒ってすらいないのだから。
今の今まで、この場の誰もが彼女の本質を見抜けなかった。忘れていた。彼女があまりにも平凡で、どこにでもいる当たり障りのない人物に見えたから。
そう、彼女にとってジェイドとは?
必要不可欠の存在だったのか?
……答えはNOだ。
例え、彼がいなくても生きていけるだけの強かさを持ち、一度見限ればどこまでも線引きがなされる。それが彼女、異世界から来てしまったユウの本質だった。
彼らはこの時ほど、彼女のことを恐ろしいと感じたことはなかった。
嫌な汗が三人の背を伝う。
「今日来たのは今後一切、ジェイド先輩と関わらないためです、それに」
「私のせいで死なれたら、寝覚めが悪いので」
「こんな格好悪い先輩、好きになるわけがないでしょう?」
彼女から初めて向けられる、明確な敵意を持った言葉の応酬。
それらがジェイドの身に、次々と風穴を開けていく。
全くもって手加減のなされないそれは、ジェイドの表情を歪ませるに十分な威力だった。
「前にも言いましたが、私は私を大切にしてくれる人が好きです。 決して試したり、愛をおし測るような人は好みではありません」
「私もですが、皆さんにもご迷惑なので、今後は連絡をお控えくださいね」
「それでは用事は済んだので……先輩方、失礼します」
彼女は言いたいことだけを端的に伝えると、パッと手を離す。
そのまま踵を返すと、振り返ることはなくその場を後にした。
ジェイドは微動だにしなかった。去り行く彼女の後姿を、見送ることしかできない。
しばらくの間、残された三人は動けなかった。声を発することもできなかった。
ようやく沈黙を破ったのは、フロイドだった。
「……うわぁ……小エビちゃん、えげつねぇ……」と、大きな独り言を口にする。
「……お前が全面的に悪いのに、なぜか可哀想に思えてきました」
アズールまでもが、ジェイドに同情しかけていた。
最愛の相手にあそこまでズタボロに言われた挙句、こっぴどく振られてしまっては、愛情深い人魚にとって致命傷だ。それは同じ人魚であり、同郷のよしみである二人には容易く理解できた。
今のジェイドは深い痛手を負って、尚且つその傷に塩を擦り込まれた状態だ。
いつ暴走しても、おかしくはない。
「……ジェイドぉ、大丈夫?」
気分屋のフロイドも、珍しく猫撫で声で片割れを気にかける。
ジェイドは静かだった。泣くことも、叫ぶことも、狂うこともなかった。
細く息を吸うと、まるで思い出したかのようにゆっくりと歩き出す。
落ちていたネクタイとジャケットを拾い上げて埃を払う。自身の着崩れた、しわが目立つシャツを魔法で直した。
困惑するフロイドとアズールをよそに、淡々と身支度を整えていく。
「……どこかに行くんですか?」
堪らずアズールが訊ねると、ジェイドは弱々しく頷いた。
そしてにっこりと、得意の営業スマイルを浮かべる。
「……僕、今から仕事をしてきます」
「───は?」
アズールの表情が引き攣り、フロイドはあからさまに顔を顰める。
ジェイドは頭のネジがいくらか抜けているタイプの、常識人の皮を被った人魚だ。
それは誰よりも、この二人が知っている。そんな彼がまさか仕事でわざと忙殺されて、失恋の痛みを忘れようとしているなんて、あまりに平凡すぎて似合わない。
「うげぇ、マジでそれ言ってる?」
「ええ、勿論……しばらくは仕事に専念します」
「だから、急にどうしてそうなる?」
アズールは眼鏡を外して、こめかみを揉む。
新たな頭痛の種の予感に、大きなため息を隠そうともしない。
ジェイドといえば、いそいそと支度を済ませ、ネクタイを結びだす始末だった。
マジカルペンを一振りして、カバンを二階の部屋から引き寄せると玄関に向かいだす。
「止めないで下さい、誰が何と言おうと出社します」
晴れやかな表情でジェイドは微笑み、黒いエナメルの革靴に足を通す。
こうなってしまえば、彼は梃子でも動かない。ジェイドの意思を曲げることは、テストでオール満点を取ることよりも、遥かに難易度が高い。アズールはジェイドを止めることを早々に諦め、眼鏡を掛け直す。
せめてもの抵抗に睨みつけても、どこ吹く風だ。
「……厄介なことには、するなよ」
「ええ、わかっています」
アズールの念押しに、ジェイドはあっさりと返事を返す。
そのまま扉開けると、家を後にした。残されたフロイドとアズールは顔を見合わせる。お互いの顔に、同じ感情が浮かんでいた。
フロイドが心底面倒くさそうに、肩を竦ませる。
「なんかさぁ、オレめっちゃ不安なんだけど」
「奇遇ですね、僕もです」
●
「乾杯~!」
各々好みの飲み物が入ったグラスが掲げられ、楽しげな声が響く。
グラスがかち合い、涼しげな音が鳴った。
今日は待ちに待った、学生時代の友人たちとのランチだった。
エース、デュース、グリム、ジャック、エペル、セベク、オルト、私を含めた八人での食事は、気張らず入れる店を選んだのだが、この選択は正解だったと思う。
久々の再会に、話は尽きない。
「えへへ、全員で集まるの久しぶりだね」
オルトはイデアの作った新しいギアを着ていた。私服チックなそのいで立ちは、街にいても浮きにくいだろう。
嬉しそうに笑う彼に、こちらまで嬉しくなる。
「ああ、二年ぶりくらいじゃないか?」
ジャックが言いながら、食事を口に運ぶ。
学生時代よりも逞しくなった身体つきは、プロマジフト選手に相応しいものへとなっていた。
「そんなに経つっけ?」
「それくらいだろうな」
エースが実感なさげに首を傾げると、セベクが至って真面目に頷く。
エースもそうだが、セベクは元の顔立ちもあり、より大人っぽい印象を受ける。まぁ、実際中身はマレウス・ドラコニア万歳! な従者バカなのだが。
「今日みんなと集まれて本当に嬉しいな、元気そうで安心したよ」
エペルは口に詰め込んだステーキを飲み込むと、元気いっぱいにニカっと笑う。
口の端にソースが付いていることを教えると、慌ててナフキンで拭っていた。
「オレ様はうまい飯が食えるなら、何でもいいんだゾ!」
「グリムは相変わらずだな」
相棒の魔獣は学生時代から、美味しい食事と楽しいことに目がない。今でこそちゃんと席に座って大人しく食べているが、当初は大変だったのだ。
そんなグリムに、デュースは苦笑した。
「みんなの近況はどう?」
「んじゃ、久々だし一人ずつ簡単に話していきますか~」
「ふな! それならオレ様から言うんだゾ!」
「はいはい、グリムからなー」
「ふふん、聞いて驚け! オレ様は────」
それぞれが自身の近況を語る中、途中横槍を入れつつも耳を傾ける。みんな楽しそうで、まるで学生時代に戻ったみたいで、心がむず痒い。各々が仕事で忙しい中、予定を調整して来てくれた。今日この日を待ち望んでいたのが、自分ひとりじゃないことが嬉しかった。
一人ずつ代わる代わる自身の近況を話し終えて、とうとうユウの番が回ってくる。
全員の顔が、興味津々にこちらを向いた。
「そういうユウはどうなんだ?」
「ジェイド・リーチとかいう男と暮らしてただろう?」
「あ、そういえばだいぶ前にジェイド先輩から電話かかってきたけど……なんかあったのか?」
デュースを皮切りに、セベク、ジャックが疑問を口にする。
それに何と答えるか迷って「うーん、まあ話せば長いんだけど……今は一人暮らしなんだよね」と話を濁し、苦笑した。
「えっっ……ジェイド・リーチさんは、ユウさんにべた惚れだったのに……喧嘩でもしたの?」
オルトが信じられない面持ちで、こちらに訊ねる。
そうか、傍から見れば彼はべた惚れだったのか……と感慨深い気持ちになった。
全てを話すのは長くなりすぎる、かと言って短すぎると納得してもらえない。
ここは簡潔に、スパッと白状してしまおう。
「ううん、喧嘩じゃなくて……ただちょっと浮気されまして………」
「はぁ⁉ マジかよ! やっぱ黒だったんじゃん!」
エースがドン引きの表情で口にすると、ほかの面々も渋い顔をする。
全員の食いつきが強くて話さざる終えず、事の顛末をかいつまんで語った。
「最低だね、それ」
「ジェイドのやつ、バカなんだゾ」
エペルは嫌悪感を露わにして呟く。
グリムまでもが呆れていた。
「許せねぇな……そんなのこっちの国じゃ、半殺しにされても文句言えねぇぞ」
「けしからんやつだ! 擁護のしようがないな!」
「あはは、みんな怒ってくれてありがとうね。 でも正直、全然ショックじゃなかったの」
「え? それはなんで?」
ジャックとセベクの容赦ない言葉から始まり、あらゆる罵詈雑言がその場を飛び交う。
当事者の自分よりも、彼らの方が何倍も怒っていることがおかしくて、思わず笑ってしまった。
オルトは一般的ではない私の感情に、理解できない様子で訊ね、小首を傾げる。
「うーん、なんでだろう……それなりに好きだったけど、終わった人との関係に悩むのって無駄じゃない?」
「うわ、出た……ユウのズバッと発言」
「気持ちはわかるけど、エースクン黙って」
そこで一度、グラスのオレンジジュースで喉を潤す。
果汁百パーセントの新鮮な甘みと酸味が口に広がり、とても美味しい。
「それになんていうか……みんなには話したけど同棲っていうより、ルームメイトって感じだったし……恋人らしいこともなかったし……だから別に痛くも痒くもないというか……」
「お前らの関係、よくわかんねーんだゾ」
「あはは、確かにね」
自身のことなのにどこか他人事のように話せば、グリムから呆れた視線を向けられる。親分ですら、子分のことは理解に苦しむ部分があるらしかった。
一瞬、沈黙が流れる。が、次の瞬間、隣に座っていたエペルがガバリとこちらに身を乗り出す。
何事かと驚いたが、表情は真剣そのものだった。
「ユウサン、何かあったらすぐに言ってね! 僕、力になるから!」
「群れるのは好きじゃねぇが……まぁ、お前はダチだからな……なんかあったら連絡しろよ」
「カチコミ行くときは言ってくれ! いつでも駆けつけるからな!」
「僕にできることは少ないけど……ネットや住居のセキュリティ構築なら任せて! いつでも相談に乗るよ!」
「ま、まぁ……話くらいなら聞かないこともない」
「ま、無理せずにお前のペースで過ごせば? ……なんかあったら言えよなー」
次々に気遣われて、その数と温かな言葉に圧倒される。まるで戦隊シリーズのヒーローがオールスターズで登場したような心地だった。
これが映画なら、一番の胸熱シーンだろう。
ジーンと痺れたように、心が温かくなる。
「みんな……心配してくれてありがとう……なんか感動しちゃった!」
「……子分は世話がかかるんだゾ」
グリムは腕を組んで、後方親分面だ。しかし、その表情は極めて優しい。
嬉しくて思わずぎゅうぎゅうと抱き込むと「苦しいんだゾ!」と身をバタつかせた。
まるで一件落着といったような雰囲気が漂っている。そんな中、空気の読めないスマートフォンが机の上でブルブルといつまでも振動していた。それにエースはちらりと視線を投げかけ、「そういえばさ」と会話を切り出す。
「さっきからスマホ、鳴ってるけど出なくて大丈夫?」
「うん、気にしないで。 うるさいから電源切っちゃうね」
ボタンを長押しすると、スマートフォンの画面が暗くなる。
それと同時に振動は止まり、先ほどまでのやかましさはぴたりと消えた。
「……急ぎの連絡かもしれないし、出た方がいいんじゃねーの?」
「ううん、全然大丈夫だよ?」
エースは再度、確認するように促した。
なんだか様子のおかしい彼に首を傾げる。
こちらが不思議そうに見ると、居心地悪そうに視線を泳がせた。
「そ、そう? けどさ、何回もかかってくるってなんか重大なことじゃないかなー……なんて……」
「ねぇ、エースクン……なんか怪しいよ?」
「え、え……そう? ただちょっと気になったというか……」
「エース・トラッポラさんのバイタルを測定、通常より早い数値を観測、加えて身体の筋肉が通常の〇.三倍強張っています」
「おい、何か隠してるだろう」
全員の訝しむ視線から逃げるように、エースはコーラをちびちびと飲む。
オルトの身体スキャンが行われたことにより、確実に怪しさの信憑性が上がった。
セベクが脅すように身を乗り出す。
「いや~……んなわけ……あはは」
「まさかとは思うが……ジェイド先輩から電話に出るように、誘導頼まれてたりはしないよな?」
ジャックがぽつりと呟いた言葉に、途端ぴたりとエースは固まる。
「あはは、ないない! ぜぇ~ったいに、ないって!」
「……オレ様でも怪しいってわかるんだゾ」
「おい、エース……白状するなら今だぞ」
あからさま動揺する彼に、グリムとデュースが白い目を向けた。
私も畳み掛けるようにして、彼の名前を呼ぶ。
「エース~?」
「っ……ごめん、頼まれました……!」
追い詰められたエースは、両手を合わせて謝った。
途端、先ほどまでの冷たい空気がどっと和らぐ。
「やっぱりな」
「バレバレなんだゾ」
「け、けどさ、聞いてくれよ! 依頼というか、フロイド先輩に脅されて仕方なくだな……!」
ジャックとグリムが呆れた様子でエースを見る。
「おい、見損なったぞ! 友人を売ったのか!」
「ちげぇって! ……俺だってやりたかなかったけどさぁ……悪かったって……」
セベクが声を荒げると、エースは耳を抑えながらも必死に否定した。
「ユウサンを傷つけたくせに、会いに来てほしいなんて……そがなことが許されるとでも思ってんのがぁ⁉」
「お、落ち着けってエペル……素がでてんぞ」
なんとかこの場を宥めようと、エースは懸命に頭を回転させる。だが、言い訳をすればするほど周りの反応は悪くなった。なんで俺がこんな目に……と半ば泣きたい気持ちで弁明する。
「……フロイド先輩からの要件は?」
そんな一部始終を静かに眺めていたユウが、エースに訊ねた。
その途端、すべての視線がこちらに向いて、険しい表情で口々に意見する。
「ユウ、こんなの取り合う必要ないぞ」
「そうだ! 自分から謝りにも来ないような男なんて見限ってしまえ!」
「僕から見ても、ジェイド・リーチさんには弁明の余地はないと思うよ」
「ありがとう、みんな……でも、もうエースを責めないであげて」
ジャックやセベクはかなり頭にきているのか、荒々しい言葉遣いでジェイドを責めた。オルトも言葉遣いはいつも通りだが、怒っているのは同様だ。想像以上にヒートアップしてしまったこの場を収められるのは、恐らく当事者のユウひとりだろう。
「ユウ……いいのか?」
デュースが気遣うようにこちらを見る。
それに頷くと、渋々といった様子で彼らは口を閉ざした。
「……ごめんな、俺が悪かったよ」
「いいの、エースも被害者だよ」
「あんがと……あのさ、一応伝えてもいい?」
「うん、お願いします」
いつになくしおらしいエースに微笑めば、ばつが悪そうに頭を掻く。
勿論、怒っていないし、こんなことでエースを嫌いになるわけがない。だてに長年、マブをやっていないのだから。それにフロイドに脅されて、仕方なくやった彼に当たるのは筋違いだろう。
「ジェイド先輩、熱で倒れて入院してるらしい」
「えっ……どうしてだ?」
「身から出た錆だな」
「自業自得じゃないか? 天罰だろう」
「まぁまぁ……みんな落ち着いて」
デュースは困惑し、ジャックとセベクは相変わらず辛口なコメントを述べる。
それをなんとか宥めると、エースはさらに話の続きを口にする。
「なんかフロイド先輩の話ではだけど……」
「うん」
「仕事を馬鹿みたいに入れてロクに休みもせず、免疫が下がってるところに季節性の風邪にかかって悪化、そんで重症化したらしいよ」
「かなり酷いの?」
「そうみたい」
───全く、つくづく迷惑な人魚だ。
ユウは興味なさげに、浅く息を吐いた。
勝手に傷ついて、勝手に倒れて、挙句の果てに兄弟やエースまで巻き込んで。
つくづくしぶとい彼にほとほと呆れを通り越して、尊敬するレベルだ。
「仕方ないか……」
「え、まさか行く気じゃないよね?」
エペルが信じられないものを見るような表情でこちらを窺う。
「そんなろくでもない奴ほっとけよ」
「……お人好し過ぎるんだゾ」
「俺が言うのもなんだけど、行かない選択肢もあると思うぜ」
口々に引き留められて、思わず笑みがこぼれた。
エースまでもが、やや心配そうにこちらを見つめる。
「ふふ、みんな過保護だなあ……」
ユウは安心させるように微笑むと「でも行くよ」とはっきり言い切った。
全員の表情が驚きと困惑で満ちていた。
「だってこんなことで、みんなとの仲に亀裂が入るのは嫌だしね」
「ユウ……」
もう、誰も引き留めなかった。
神妙な顔つきで表情を曇らせる。ただ「何かあったらすぐに言え」と各々の言葉で伝えられ、固く約束させられた。それにしっかりと頷き、にっこり笑う。
ご機嫌なのは、この場でユウただ一人だった。
「ところでエース、病院名と病室の番号は?」
●
「ごほっ……げほッッ……はぁ……」
咳をしすぎて喉が痛む。喘息の発作の様に、一度咳が出るとなかなか収まらない。なんとか身を起して、ベッドサイドの水を流し込む。カラカラの口内が一瞬だけマシになったが、それもすぐに元に戻る。干上がった砂漠のごとく、すぐに喉奥がパサついて、また激しい咳が出た。このままでは喉がおかしくなりそうだ。
手元のペットボトルに入った水は、もうあまり中身がない。片割れのフロイドが用意してくれたもので、唯一喉を通ったゼリーも空になっていた。熱のためか思考が定まらず、だるくて仕方ない。始終悪寒がして、身体がまともに動かなかった。
ようやく咳が止まると、なんとか胸元を擦る。普段丈夫なジェイドでも、少々堪える痛みとしんどさだった。
再度身体をベッドに預けると、咳が少しでもマシになるように横になる。
ヒューヒューと喉から呼吸に合わせて、音が聞こえた。
苦しい。痛い。つらい。
様々な感情と身体の不調に耐えながら、目を瞑る。早く眠りにつきたかった。眠ってしまえば、少しは楽になれる。彼女のことも忘れられた。嫌なことや苦しいことも一瞬だけ逃れられる。焦点の定まらない視界で、点滴の液体がぽたりぽたりと伝って落ちる様子を眺めた。
きっとこれは罰だろう、とジェイドは思う。
彼女の優しさを試して、愚かにも傷つけた。
己の醜い幼稚な感情で、あんなにも大切な彼女のことを踏み躙った。
真心を、献身を、信頼を、仇で返した。
そんな自分が高熱に苦しみ喘ぐ姿は、実にお似合いだと思えた。
遠のいていく意識の中で、彼女の名前を呟く。
いっそのこと、このまま死んでしまいたかった。
「……ん」
いつから眠っていたのか、あまり覚えていない。
身動ぎすると、額から何かがずり下がった。何かのせられていることがわかる。大方、誰かが見かねて濡らしたタオルを置いてくれたのだろう。先ほどよりも随分と身体の怠さがマシになっている。少し熱が下がったらしい。
「あ、起きたんですね」
それまで誰もいないと思っていた部屋に、ひどく懐かしい声が響く。
幻聴かと思った。
まさか、そんなはずはない。とうとう、頭がおかしくなったのだ。そうに違いない。
混乱する頭で声の主がいる方を向く。が、タオルが邪魔で何も見えない。
僅かに指先が触れて、目元にずり下がっている濡れたタオルを持ち上げられた。視界が一気に明るくなって、目を瞬く。
「……ユ、ウ……さ、ん?」
光に目が慣れると視界が鮮明になった。
そこには、やはり彼女が佇んでいた。
何も言わずに冷水に浸していたタオルを持ってきて、再度ジェイドの額に乗せる。火照った身体にひんやりとして気持ちがよかった。思わず肩の力が抜ける。
「何か飲めそうですか?」と彼女は訊ねた。
至って以前と変わらない態度だった。優しい穏やかな声色に、柔和な笑み。
なんて自分に都合のいい幻覚だろうか、と内心毒づいた。けれどそれと同時に、もう幻覚でもいいかと思えた。ここまで落ちたら、落ちるとこまで落ちてしまおう。
「……は、い」
「あはは……酷い声ですね」
喉奥からなんとか声を絞り出したが、かなりガラガラだ。
それに彼女は困ったように微笑んで、ジェイドの背に手を添えて支える。
節々が痛む身体をゆっくり起すと、ユウはその角度にベッドの背もたれを横付けのボタンで調整した。
「病院のベッドって、これができるから便利ですよね」
彼女は持参したであろう紙袋から、ベッドサイドのテーブルにいくつか飲み物を置く。スポーツ飲料や紙パックのリンゴジュース、野菜ジュースなどバラエティー豊かな品揃えだった。ふと横を見ると枯れかけだった花瓶の花も、いつのまにか新しいものに変わっている。きっと彼女が取り換えたのだろう。
「どれにしますか?」
「そ……それで」
「リンゴジュースでいいですか?」
「はい」
「どうぞ」
指さした紙パックのリンゴジュースに、ユウはストローを刺し手渡した。
おずおずと受け取ると、口に含む。
優しい林檎の甘さが口内に広がって、ゆっくりととろみのある液体が喉を嚥下する。
「おい……し、い……」
「よかったです。 それ、エペルの村のリンゴ農園で作られたものなんですよ」
ユウはまるで自分が褒められたみたいに、顔を綻ばせる。
ジェイドは呆気にとられながら、これが幻覚ではないことに薄々感づいていた。けれど、本物か確かめることはできなかった。
怖かったのだ、とても。
ジェイドには自信があった。彼女を、ユウを見間違うはずがない。
けれどもしも彼女じゃないなら、一体この人間は何だというのだろう。
今、目の前にいるこの女性は。
「ユウさん、なんですか?」
「はい、そうです」
「な、何の御用でこちらに……もしやお知り合いが?」
「ジェイド先輩のお見舞いに来たんです、体調が悪いそうですね」
彼女は微笑みを浮かべて、近くの椅子に腰掛ける。あんな別れ方をしたのに、ちっとも気にしていないようだった。ジェイドだけがうじうじと悩み、後悔し続けていたのだと思い知らされたような気分だ。
以前にもまして美しくなったユウと、痩せてやつれた自分。
その対比が残酷に現実を突きつけてくる。彼女はジェイドがいなくても生きていけるのだと、今の姿が物語っていた。
「お願いだから、帰ってきてくださいませんか……」
言うつもりのなかった言葉が、口からこぼれ落ちる。
彼女の顔をまともに見ることができなくて、俯いた。
くしゃり、と顔が歪んでいく。声はみっともなく震えていた。
両の目から大粒の水滴が落ちて手元を濡らしていく。
「あなたがいないと、僕は死んでいるみたいなんです」
「何を食べても美味しくないし、何をしても楽しくない、つまらない、さびしくて……」
「毎日泣きたくなるのを必死で堪えて、それでもずっと、あなたのことが頭から離れなくて」
「……もう、どうにかなってしまいたい」
ぐちゃぐちゃと濁った感情を、思いのままに吐き出した。
上手く言葉がまとまらない。
彼女はジェイドの泣き言を否定も肯定もせずに、静かに聞いていた。
仕草も、所作も、声も、雰囲気も、縁取るすべてが彼女そのものだった。啜り泣くことしかできないジェイドに、ユウは小さく息を吐く。
びくり、とジェイドの肩が揺れて縮こまった。
「随分、やつれましたね」
予想に反して、ひどく優しい声だった。
ジェイドの頬にユウの指先が触れる。
顔を上げると、伝う涙が彼女の指先を濡らした。
「ええ、ほんとうに……あなたは前より綺麗になった」
「……そんなにご自分を追い込まなくても良いのでは?」
ジェイドが困ったように泣き笑うと、彼女は頬を親指の腹で柔く撫でる。
まるで幼子をあやすような仕草だった。弱々しく、彼女の手を握る。
「仕事に没頭するくらいしか、あなたを忘れる方法がなかったんです」
「それは、難儀ですね」
彼女は困ったように微笑みを浮かべる。
ユウは、彼の手を振り払わなかった。
正しくは、振り払えなかった。こんなに弱って、やつれた彼を見ていたら、なんだかどうでも良くなってしまったのだ。
指先で彼の瞳からボロボロと溢れる涙を拭っても拭っても、間に合わない。
「せめて、せめて……友人になってくれませんか?」
「お願いします、どうか……」
ジェイドは祈るように彼女の手を包み込み、額に当てた。瞼を閉じて、呼吸を繰り返す。それはまるで、ユウに導いてくれと言っているようだった。消え入るような彼の懇願に、ユウは大きくため息を吐く。
「……友人なら、元気になってからですね」
ぽつりと溢された言葉に、ジェイドは大きく目を見開く。
泣いているのに、喜びの色が表情に滲む。
口元が綻んで、ガラガラの声で「三日でなんとか元気になります!」と宣言する。まるでこの世で一番幸せだとでも宣いそうな勢いだった。
「私、無茶をする人は嫌いです」
「わかりました、医師の言うことを聞いて一週間は安静にしています」
ユウの言葉に途端、真顔で先ほどの意見を容易く曲げた。その様子が素直過ぎて、思わず笑ってしまう。
しょぼくれたジェイドの喉がクルルと鳴って、余計に可笑しかった。
それからしばらくして、コンコンと控えめなノック音が響く。入ってきた看護師は嬉しそうにはにかむジェイドを見て、何も言わず微笑んだ。点滴のパックを交換すると、面会時間の最終時刻を伝えて部屋を出ていく。
「あと三十分で帰らなきゃですね」
「……あの……もし、嫌でなければ最後に……手を握ってくださいませんか?」
ジェイドはおずおずと恥ずかしそうに呟くと、身を横たえる。
また熱が上がってきたようで、しんどそうだった。
濡らしたタオルを額に再度掛けてやれば、目を瞑る。
彼の大きな手のひらに、ユウは手を重ねた。
指先に力を込めると、彼も弱く握り返す。
「熱の時って人恋しくなりますよね」
「ええ、本当に」
ジェイドは困ったように笑った。
今日の彼は素直で少し可愛く思う。
「仲直りです、先輩」
「恋人は無理ですが、友人になりましょう」
ユウの言葉にジェイドは目を開く。そして、また瞼を瞑った。繋いだ手に僅かな力が込められる。
「今はそれでいいです」と呟いてジェイドは身体の力を抜く。緩く息を吐きだすと、安堵の表情で微笑んだ。
「あなたと会話できるだけで、ひどく落ち着く」
「重症ですね」
ユウは笑った。
ジェイドは笑わなかった。
「それくらい、一途なんです」
微笑みを浮かべたまま、彼はすっと目を閉じる。
このまま死んだとしても、ジェイドは構わない。
傍らに愛した女性が、恋人がいるだけで、こんなにも満たされる。
いつのまにか毒牙を抜かれていたのは、ジェイドの方だった。そんな彼の心中など露ほども知らず、彼女はまた小さく表情を綻ばせる。
「ふふ、それはジョークですか?」
それにジェイドは緩くかぶりを振って、彼女に優しい眼差しを送る。
彼女が信じなくても、これだけは伝えたかった。
ユウの頬にかかった髪を指先で耳に掛けて、ジェイドは密やかに呟いた。
「いいえ、僕の本命は後にも先にもあなた一人ですよ」
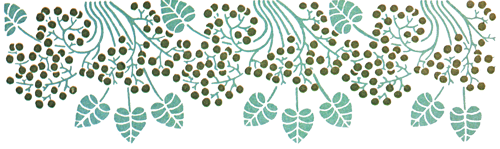
仏の顔も三度まで
こんばんは。今回の話は可哀想なジェイドが見たくて仕方なかった結果、生まれた産物です。甘さも控えめです。いつになったらイチャイチャなあま~い話をかけるのか……その謎を解き明かすべく私はアマゾンの奥地へと向かった…… 冗談はさておき、卒業後が舞台のお話です。ジェイド26歳、監督生25歳とかなり大人になった二人です。悪しからずご了承ください。
また、作品の感想や質問などございましたら、下記のURLからお題箱に何卒お願い致します。特に感想は大変励みになっているので、お気軽に送っていただけると嬉しいです。
https://odaibako.net/u/Pendragon_001
