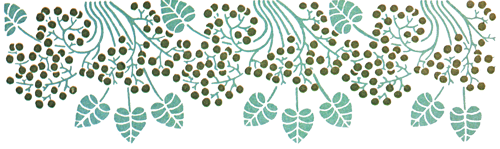茹だるような熱さのさなかにいた。
放課後のガーゴイル研究会に半ば強引に連れ出され、あれやこれやと教えてもらっても内容がほとんど頭に入ってこない。もはや会話の合間に相槌を打つだけのロボットになってしまっている。いつもはそれなりに楽しめる彼の熱意に溢れた解説も、今や右から左へと流れていく雑音となってしまっていた。
ほどなくして私達は早々にガーゴイル研究会の活動を切り上げ、購買へ足を運ぶ事となった。
「今日こそ溶けるかもしれない…」
「ほう、それは困ったな」
私は涼し気な表情を浮かべる隣の友人に不満を溢す。彼は至って平然としていて、ボタン一つ緩めない。大したものだ。
「溶けたら全部掬い集めて魔法で固めてね…」
「お前は本当に飽きないな」
クツクツと愉快そうに喉を鳴らす。彼にとって私の戯言なんて気にするに値しないものなのだろう。ふとなんとなしに見上げればこちらをじっと見つめていて、突然フッと目を細める。
「な、何か?」
「しかし…お前は失うには惜しいからな、そうするとしよう」
冗談なのか本気なのかわからない発言に困惑しつつ、彼ならやりかねないなと思われた。それを成し得るだけの技量も知識もある。なるべく溶けないように気をつけねば…。
そうこうしているうちに購買に着いた。
夏の定番商品ともなれば置いていないはずもなく、難なく手に入れることができた。まぁ、サムさんのお店に置いていないものの方が少ないだろう。皆まで言わなくても目当てのモノは用意されているくらいだし。
そうして色とりどり、様々な味の氷菓を悩んだ末に各々一つ手に取りお代を支払う…筈だったが代金を払おうとしたところで手で軽く制されて彼が奢ってくれた。
私の国では…というよりも私の住んでいたところは恋人や特別な仲でもない限り、割り勘や別々で支払うのが普通だったので文化の違いを感じて新鮮だ。購買を後にしながらお礼を伝えると彼は満足気に頷いた。
木陰のベンチに並んで腰掛け、アイスの包装紙を破る。するとひんやりとした冷気の靄をまとった氷菓が顕になった。一口齧るとなんとも言えないシャリシャリとした食感と柑橘類の風味が口に広がる。舌の上でひんやりとしたものが徐々に溶けて喉をするすると下っていく感覚は心地よかった。
隣のツノ太郎はカップアイスを選んだ。ひとさじ掬ってはゆっくりと口に含み、味わっている。その姿はただアイスを食べているだけなのにとても様になっていて、棒付きアイスを選んだことを少しばかり後悔した。せめてカップアイスならもう少し品良く見えたかもしれない。
私はどうにも彼の隣に座るといつもより背伸びしたくなるきらいがある。見栄を張るのはあまり良いことでないけれど、きっと見劣りしたくないのだ。彼と対等な立場でいたいと思っているからこその行動だと思う。そんな考え事をしていたら先程まで形を保っていた氷菓が溶けて滴り始めた。
「わわ…やばい…溶け始めた」
手にポタリと次々に冷たい滴が落ちて指の間を伝っていく。「最悪だ〜」と唸りながらベタベタする手の不快感を少しでも減らすべく、急いで食べ進める。その様子を彼はじっと見つめていた。
「手伝ってやろうか?」
「え、ほんとに」
あまりに慌てているので見兼ねた彼からの思わぬ提案に食い気味に返事を返す。これは得意の魔法で氷菓を冷やしてくれるとみた。
「ああ」
「助かるよ!ありがとうツノ太郎」
もはやボタボタと手に落ちる滴を止めるすべがない私は彼が救世主に見える。いつだって魔法を見るのは好きだ。今回はどんな風に魔法をかけるんだろう…なんて期待して待つ自分がいる。
彼は自分のカップアイスを魔法で浮かばせておいて、氷菓を持つ私の手を優しく引き寄せた。
そしてそのままま身を屈めると滴る水滴を舐めとった。ぞわりとした感覚が背を一気に伝う。痺れにも似たその感覚はツノ太郎の舌が這うゆっくりとしたスピードとは反対に、身体中をあっという間に支配する。
「ぁ…あの…」
「なんだ?」
吐息が指先をくすぐり、思わず息が詰まる。
溶けていく氷菓は止められない。
「ぇっと…ちょっとくすぐったい…っ…ぅ…」
「手伝えと言ったのはお前だが…?」
「いや…そ…じゃな…っ…くて…」
滴るのはひやりとした水滴なのに指先を焦らすように舐めとる彼の熱に浮かされてしまいそうになる。手を引っ込めようにも、しっかりと掴まれていてびくともしない。周りに他の生徒がいないとはいえ、あまりにもこの状況は不味い気がする。仮にも一国の次期後継者が…その…言い難いがこんな誤解を与えかねないことをするのは非常に良くないと思う。それにこのままだとセベクに見つかったとき、何と言われるか考えるだけでもゾッとする。爆音の怒声が飛んでくることはまず間違いないだろう。
「っ…いた…」
ピリッとした痛みが指先を刺激した。
ちらりと指先を見れば、意識を他所にやった隙に柔く噛まれたのだと気付いた。
「…僕がいるのによそ見をしてうわの空だったからな」
不服そうに呟いた彼はまるで幼子のようで苦笑してしまう。
「えぇ…マレウス子供みたいなこと言うね…」
「子供はこんなことはしないが?」
そう言って指先を伝う滴を舐めとり、食み、口づける。ゆっくりと挑発するように微笑んだ彼が寄越した艶めかしい視線に思わずたじろぐ。
「そ…それはそうかも…」
もはや真っ赤になっているであろう顔をなんとか少しでも隠したくて、俯いた。
これは海外…というか、この世界では普通のスキンシップなのだろうか。
随分と大胆すぎやしないか。もうこれ以上はキャパオーバーだ。
手や指先から伝わってくる生々しい感覚を逃がすようにぎゅっと目を瞑る。しかし、余計に神経が研ぎ澄まされて舌が這う様子がありありとわかってしまい逆効果だ。
「あの…ツノ太…郎…も…ぅ…」
熟れた果実のように耳まで真っ赤になった彼女に満足したのか、軽いリップ音を鳴らして指先に口づけを落とす。一瞬目の端で何かがチカっと光った気がした。
「名残惜しいが…どうやら降参のようだな」
「…さっきからずっと白旗上げてるのに離してくれなかったのはマレウスでしょ」
恨めし気に呟けば、まるで他人事のようにさらりと受け流す。
「どうした、拗ねたか」
「いや、あの…悪戯が過ぎるのでは…もしも他の生徒…特にセベクにでも見られたら私の命が危ないんだけどどう責任取ってくれるんですか!」
建前の後に思わず本音が漏れる。いつ何時セベクやシルバーが飛び出してくるかわからないのになんて危険なことを!と頭を抱える私を見て楽し気に笑う。
「はははは、そんなことを気にしていたのか」
「そんなことって…私にとっては死活問題だよ」
「ふふ、案ずるな…きっと今回からは何もお咎めはないと思うぞ?」
「それってどういう…」
含みを持たせた言い方になんとなく違和感を覚えるが、彼は答える気はないらしく話題を変える。まぁ、何もないならそれに越したことはない。
「それにしても棒付きアイスもなかなかいけるものだな…今度は僕もお前と同じものを買うとしよう」
「あ、気に入った? 柑橘類美味しいよね」
「ああ…爽やかな甘さと酸味が美味だった」
「マレウスが棒付きアイス…なんかあんまりイメージないな…」
「そうか?」
「うん…あ、手がベタベタだ…洗いに行きたい」
先程散々舐めとられた指先は溶けた氷菓のせいでベタベタとしていて気持ちが悪い。早く洗いに行きたい一心で立ち上がると急に手を引かれ、またベンチに戻される。
「僕が食べ終わるまで少し待て」
有無を言わせぬとばかりの視線が痛い。彼は魔法で空に浮かべていたカップアイスとスプーンを手に取るとまたゆったりとした動作で口に含む。
「はー、仕方ないな……ん?」
「どうした?」
たまたま視線を投げた指先に意識が集中した。
左手の薬指、そこに明らかに先程はなかったものが光っている。
「あの…これ…」
「その…指輪なんて私つけてったっけ…?」
「ああ、さっき付けた」
けろりとした表情でさも当たり前のように言ってのける彼を困惑の表情で見つめ返す。
左手の薬指、そこには上品に光る銀色のリングがはめられており、黄緑色の石がはめ込まれていた。
「え、なんのために?」
思わず溢れ出た言葉にいたずらっ子のような表情で彼は微笑んだ。
答えはない。ただ、ふっと息を漏らすと熱心に見つめられる。なんだか居心地が悪い。
「それを付けていればセベクもシルバーもきっとなにも言ってこないぞ」
「え、本当に?」
「ああ、保障しよう」
「それならしばらく付けておこうかな」
「ふふふ、それがいい」
よほど機嫌がいいのか今日は彼がよく笑う。私もつられて表情を緩めた。もはやほとんど原型の残らない、今にも棒から剥がれ落ちそうな氷菓を一口で食べ終えると火照った身体に心地よい冷たさが染み渡っていく。まぁ、指先を舐められたことや指輪に特に意味はないのだろう。彼の気まぐれはなんとも心臓に悪い。
後日、薬指の指輪に気付いたセベクから「何故、貴様がその婚約指輪を!?!?」と驚愕の叫びを浴びせられその場が騒然となるのはまた別のお話。