「アーシェングロット先輩、写真を一緒に撮ってもらえませんか?」
たまたま声をかけられて逸れた意識が浮上する。声のした方を振り返ればゴーストカメラを手に携えた監督生が微かに微笑んでいた。彼女の意図はわからないが、件のイソギンチャク事件のことがあってからというもの接点なんて一つもなかった。むしろ、作ろうともしなかった。けれどオーバーブロットしてしまった僕を既の所で救い出し、あまつさえ僕のことを稀代の努力家だと何の気なしに言い切った、イレギュラーな存在。今なら自らの行いに問題点があったことは否めないのも理解できる。ただ、自業自得とはいえ、後悔はない。なにせ、あの出来事があってからというもの、心が幾分か軽くなったので。
「唐突ですね、なぜ……僕に?」
「さぁ、そこにいたから……ですかね」
ひやりとした視線を投げかけても彼女はびくりともしない。
他の生徒なら、大半はこの射貫くような視線に耐えかねて逃げ出すというのに。
「全く……僕に堂々と本音を包み隠さず言うのはあなたくらいですよ」
「お褒めにあずかり光栄です」
「はぁ、褒めているわけではないのですが……」
彼女の至って真面目な表情から冗談を言っているようには見えない。
相変わらず、思考回路が読めない。謎の多い人物だ。
「それで、撮っていただけますか?」
彼女は再度、僕に問う。
そこに催促するような含みは感じない。
もしも断れば、すぐにでも納得して去っていきそうな、そんな軽い問いかけ方だった。
「もしかして、写真一枚撮るのにも対価を取ったりしますか?」
「まさか、僕はそこまで狭量じゃないですよ」
ばつが悪そうにおずおずと申し出る彼女の様子は少し、面白かった。
しかし、あまりに商人としてのイメージが強すぎるのも問題だな、と胸の中で独り言ちる。
不満げに異を唱えれば、しかし彼女は安心したように笑みを深めただけだった。
「ふふ、それならよかった。生憎、お渡しできるような対価は持ち合わせていませんので」
彼女が何も持ち得ないことは誰もが知っている。
ただでさえ、学園長からの資金繰りで苦戦している彼女から搾取しようとは思わない。流石のアズールでも良心が咎めた。
「ゴーストカメラです、使い方はご存じですか?」
「いえ、あまり……詳しくはありませんが……シャッターを押せばいいのでしょう?」
「はい、まぁ形や機能はただのカメラと変わりないのでそれで大丈夫です」
そこまで喋って、彼女は廊下を歩く生徒に声をかける。
声をかけられた彼は振り返ると、こちらに向かって……もとい、監督生に手を振った。随分と仲がいいのだな、と大して仲の良くないアズールは謎の疎外感を感じる。それが少し癪だった。
「ちょっと待っていて下さい、あの生徒に撮ってもらうように頼んできます」
監督生は彼の方に駆けて行くと二言、三言会話を交わす。
それだけで話は通じたようで、彼は頷く。ゴーストカメラを手渡された彼と監督生がこちらに戻ってくるまで然して時間はかからなかった。
「じゃ、撮りまーす」
ゴーストカメラのピントを調整し終えた彼は少し前に屈んでカウントダウンを始める。
「さん、に、いち……はい、チーズ!」
パシャっと音がして一瞬、柔らかい光に包まれる。
あまり友人に恵まれなかった幼少期のこともあって、写真など撮ることも撮られることもなかったが、今回は上手く笑えていただろうか。いつもなら嘘っぱちの笑顔をいくらでも貼り付けられるのに、ぎこちない笑みになっている気がした。そもそも、笑っていたかさえ怪しい。仏頂面のままだったかもしれない。
そんなことを気にしている僕のことはそっちのけで、彼女は写真の確認に勤しむ。
出てきたフィルムを軽くひらひらと揺らして乾かした彼が、監督生の前に写真を差し出すと二人してそれを覗いていた。
「どうかな?」
「とってもいい感じだよ、ありがとう」
「じゃ、俺はこれで」
「うん、また授業で」
あっさりとした別れだが、親しい間柄なのは見て取れた。
つい、嫌みのように口から言葉が出てしまう。
「彼とは親しげでしたね」
「彼は同じ学年のクラスメイトなんです」
「気さくないい子ですよ」
「そうなんですか……まぁ、腹の底はわかりませんがね」
彼女が思い出したように微笑むのを横目で盗み見ながら、少し意地の悪い返しをしてしまう。
案の定、表情に困惑の色を浮かべていた。
「うわー、捻くれてますね、先輩」
「この学校に通っている時点でお察しでしょう」
「……まぁ、それを言われると何も言い返せませんが……」
図星を突かれて、気まずそうにする彼女を見ているとなんだか気分がよかった。
我ながらなんと良い性格をしているのだろう、とため息が出てしまいそうだった。
だから、昔から可愛げがないだの言われてしまうのだろうが、それは僕の知ったことではない。
「……他の生徒とも写真を撮っているんですか?」
ふと、気になって口に出す。
「ええ、まぁ……そうですね」
彼女はぼんやりとした答えを返す。
監督生にとってそこはそれほど重要ではないのだろう。
「それは学園長に頼まれたからですか?」
「……いえ、それもありますが……これは、ほぼほぼ私情ですね」
「……お聞きしても?」
「先輩が期待するような秘密なんてありませんよ?」
「そんなこと、はなから期待していませんよ」
「あはは、それもそうですね」
言うか言うまいか悩む素振りを僅かに見せたが、彼女は言うと決めたらしい。
五月の爽やかな風が二人の間を通り抜ける。彼女の長い髪が風になびいた。
陽光が一瞬、雲で遮られる。
「……私はこの世界の住人でないことはご存知でしょう?」
「……ええ」
「元いた世界には、思い出やその痕跡が沢山あります。けれど、ここでは何もない。
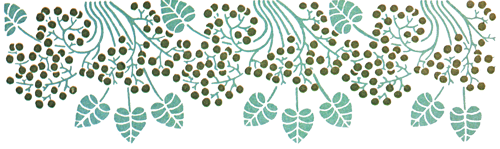
彼女のトロイメライ
【お題|カメラ越しの/に】
今回は初めてtwitterでワンドロに参加しましてその作品になります。カプ要素は薄めですがちゃんとアズ監なのでそこは安心していただいて大丈夫かと思います多分。今度はもっとイチャイチャした内容のお話を書けるようになりたいです。
また、作品の感想や質問などございましたら、下記のURLからお題箱に何卒お願い致します。特に感想は大変励みになっているので、お気軽に送っていただけると嬉しいです。
https://odaibako.net/u/Pendragon_001
彼女は両の手でゴーストカメラを大事そうに持ち、それに視線を落とす。
寂寞とした面持ちで語る監督生に、なんと声をかけてよいのかわからない。いつもなら饒舌な口も上手く回らない。その様子をただ押し黙って見守ることしかできない歯痒さがあった。
「それがたまにちょっとだけ寂しくて……でも、それなら作ればいいと思いつきました」
「だから、学園で親しくなったり何かの縁で顔見知りになったりした生徒や先生、ゴーストには一緒に写真を撮ってもらってるんです」
「アーシェングロット先輩との縁は……最初こそ印象は最悪でしたが、今となってはいい思い出です」
はにかんだ彼女の微笑みにちくりとした痛みを覚える。
彼女にとって、この写真はそこらの若者が軽いノリで撮ったものとは違うのだ。
この写真に意味を、居場所を、自身の存在を見出し、そこに生きていたという証を刻む。例え、傍から見れば何気ない日常の一枚も、彼女にとっては宝物で大切な歴史なのだろう。そう理解してしまったら、すとんと腑に落ちた。そして彼女のその在り方を好ましく思ってしまう、自分自身にも驚いた。
けれど、器用で不器用なアズールはそういった本音を吐露することに躊躇いがあったのでいつものように墨 を吐く。
「……それ、本人の前で言いますか?」
「本当のことなので」
それでは、と暇を告げようとした彼女の腕を掴んで引き留める。
「……僕からもお願いがあります」
「なんでしょうか?」
「あなたの写真を、そのカメラで撮らせてください」
「え、なんでですか……」
怪訝な表情で明らかに警戒する彼女に僕はわざと考え込む真似をする。
「さぁ、そこにいたから……ですかね?」
「……真似しましたね、卑怯です」
「ふふ、卑怯も何もあなたが最初に言ったんですよ?」
「……口では先輩に勝てる自信がありません、好きにしてください」
がっくりと肩を落とし、降参の意を示すように両手を上げた。
その手からゴーストカメラを受け取って、アズールは営業スマイルを浮かべる。
「ええ、そのようにさせてもらいます」
監督生が居づらそうにこちらを見つめている。
それをカメラのレンズ越しに眺めながら、ピントを微調整していく。
すると少しだけぼやけていた視界がクリアになって、完全にピントが合うと監督生の姿が鮮明に映る。
それを合図にアズールはシャッターを切る準備を始め、監督生に声をかける。
「もう少し後ろに下がってください、ええ……そのまま……撮りますよ」
「はい」
「さん、に、いち……」
監督生が微笑んだ瞬間を狙い、シャッターを切る。
パシャりと音がして、一瞬光が視界を覆った。
フラッシュで極僅かな間、見えなかった世界はすぐに色を取り戻した。
「上手く撮れましたか?」
彼女は穏やかな表情で僕に問いかける。
その表情の下に抱えた想いなんか微塵も感じさせない、そんな顔。
彼女のことなんかこれっぽっちも知らない僕らにとっては見慣れたいつもの表情。
それに少しの嫌悪感を覚えながら、にこりと笑みを張り付ける。
「ええ、よく撮れていますよ」
「───この写真、いただいても?」
「構いませんよ、私も一緒に撮ってもらいましたし」
然して気にした素振りもない彼女はにこりと笑って簡単に了承した。
きっと彼女はフェアトレードだ、なんて思っているのだろう。
「アーシェングロット先輩、ありがとうございました」
「ええ、では」
静かにゆったりとした足取りで去っていく彼女の後姿を見送って、僕は手元の写真に視線を落とす。
校舎内、廊下、中庭の新緑を背にして木漏れ日の中で、微笑む彼女の姿が眩しくて寂しかった。
僕のことを散々振り回しておいて、あんなに嫌だった幼少期から今に至るまでの僕を肯定しておいて、今までのオーバーブロット事件を解決し、それだけのことを成し遂げておいて、それでも彼女にとって僕らは蚊帳の外の存在で。いつか元いた世界に帰る日を夢見てそれでもこの世界に居場所を求め、爪痕を遺そうともがく。その様は酷く愛らしくて、憎らしかった。だから、せめて僕だけは彼女の痕跡を手元に残したいと思った。彼女がこの世界に確かに存在し、同じ学び舎で過ごしたという事実と歴史を誰もが忘れても、僕だけは忘れたくない。
────いや、忘れちゃだめなんだ。
ブレザーの内ポケットから手帳を取りだすと、その写真を丁寧にはせてしまう。
彼女が元いた世界に帰る日が来たとして、月日の流れに記憶が攫われてしまっても、この写真を見るたびに思い出せばいい。
「──絶対に、忘れてなんかやるか」
